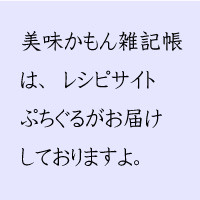ビリケンとは何か
ビリケンは、アメリカの女流美術家E.ホースマンの夢によって作られただ。 ある日夢に妙な神様が現れ、自分の姿の像を作り、その足を掻けという。 あくる日、そのとおりの像を作り、よくある男性の愛称「ビリー」と「ケン」をくっつけて「ビリケン」と名づけた。
(読むクスリ 30より)
ナンバ
江戸時代まで一般庶民は走れなかった。とか、昔の剣豪に関してのまるで漫画のような武勇伝は話だけ聞くとどうもウソ臭いというか馬鹿らしくもあるが、甲野氏の文章がわかりやすく、読者を無理に説得しようとしていない所がないので読んでて非常に面白い本であった。
著者は年中着物、どこへ行くにも着物一本で過ごす、と断言している。 その理由は、なんとボタンが嫌いだから。 それだけなのだそうだ。
【グッときた所を引用】
「芸術は何故尊いのか?」それは今も昔も手段が変わらないからである。 武術にも通ずるところがある。
日常生活で当たり前の事とは、時代がすぎると一番忘れ去られる。
「ナンバ」でおなじみ甲野 善紀先生の本『武術の新 人間学』より。
〒の由来
郵便マークに〒を使用しているのは日本だけなのだそうだ。
明治20年、郵政省の前身である逓信(ていしん)省は、T(ていしんのT) を郵便徽章(きしょう)とすることを決めて告示した。ところが告示したあとになってTの字は、郵便連合加盟国間で料金不足の場合に使うマークだということがわかった。
あわてたお役人は、初代逓信大臣榎本武揚にお伺いをたてた。 彼は筆を取ると、Tの字の上に一本線を書き足して〒とした。これならば逓信の頭文字 テ をそのままとったことになる。
後に官報で、「先に告示したT字形は〒の誤植」と知らせたそうだ。
(読むクスリ16巻より)
甲子園の砂
甲子園の高校野球で、負けたチームが砂を持ち帰るが、あの砂は中国の福建省より買い付けているのだそうだ。
その砂は白砂と黒土が混合されたもので、春は雨が多いので水はけをよくするために、砂と黒土の比率を6:4とし、
夏は日差しが強く、白球が見えにくいので砂と黒土の割合を4.5:5.5とする。
ちなみにプロ野球のナイターでは砂と黒土の割合を4:6としている。
アラブでは
「金を湯水のように使う」という表現は、日本とあべこべ。 砂漠に住む人たちにとって湯水はとても貴重で、一滴も無駄にしてはいけない。 それと同じようにお金も大事に使う、という意味だそうな。
アラブの遊牧民「ベドウィン」にとって水は命と同じぐらい大事なので、こんなプロポーズのセリフがあるそうな。
「僕は君が水よりも好きだ」
(読むクスリ26より)
100万ドルの夜景、香港
それは航空機のパイロットが空港の滑走路を見失わないように、市内の灯を点滅させてはならないという規則があるのだそうだ。
-読むクスリ13より-
お母さん休め
たしかになにかと毎日忙しいお母様方にはたまに休んでもらったほうがよいのではあるが、この「お母さん休め」は、そんなダイレクトな意味ではない。
「さしすせそ」が、さ→砂糖、し→塩、す→酢、せ→醤油、そ→味噌であるのと同じようなかんじで、すっかり普及してしまった手抜き料理の頭文字を並べたものである。
お→オムレツ、かあ→カレー、さん→サンドイッチ、や→焼きそば、す→スパゲチ、め→目玉焼き。 と、なるのだそうだ。 しかし、これにはオイ的に異論を唱えたい。 第一、ちょっとムリがある料理のチョイスのように思われる。 料理っちゅうものはそんなにカンタンなものではない。
・オムレツだって、一筋縄ではいかない。 →オムレツの作り方
・日本人のカレーに対するこだわり方は、ラーメン同様ハンパではない。 →カレー
・サンドイッチにもイロイロあるし。 →キューカンバーサンドイッチ、 →BLTサンド
・焼きそばもそうだ。 →焼きそばの作り方(近日公開)
・スパゲチもアル・デンテやソース作りが大変だし。 →スパゲチミートソース
目玉焼きなんて、ちゃんと作ろうとすると大変である。 目玉焼きの作り方→
とまあ誰が選んだのかは知らないが、この「お母さん休め」に選定された料理たちをオイは「手抜き料理」なんて呼びたくはないわけである。 これらの料理だって、ちゃんと作れば「おふくろの味」になりえるハズである。
ちょっと脱線。 先日カラオケに行こう行こうと誘われて、シダックスへ連れて行かれたわけである。 いいだしっぺのS氏は、桑田ケイスケのものまねをしながらサザンを熱唱しまくり、年代のギャップを感じさせてくれるし、M氏は「大阪で生まれた女」が、大好きだからと、2曲連続で入れちゃってさぶーい空気を作り出してくれるしで、大変だったわけであるが、フとしたことで、朝食を「食う食わないあなたはどっち?」という話題がもちあがる。
酒飲みばかりの席なので、「食わない派」が多かったわけではあるが、オイは食う派なわけだ。 しっかりと朝飯を食って、いままで大きくなってきたわけである。 これは今後も変わることない姿勢である。
朝食を食う派にも、パン派とご飯派がいるわけで、日本人では圧倒的にご飯派が多い(ご飯8:パン2 – 内閣世論調査による)
ご飯派ならば、白いご飯にお味噌汁、納豆に生卵に海苔、豆腐、お新香、焼き魚あたりが定番か。 パン派ならばトーストにハムエッグにトマトジュースとか牛乳とか。
しかし長い人生、そんな決まりきった朝食ばかりでは退屈である。 同じものばかり食ってるから、朝食抜きになるのかもしれないといえなくもないような気がしないでもない。 そこで、一汁十菜からなる「完全な朝食」というのを考え出した人がいる。 神田精養軒 前社長の故望月継治氏である。
まず汁はというと、季節の野菜やしじみを入れた味噌汁。 作るのが面倒な場合は、牛乳でよい。
以下十菜。
- ちりめんじゃこ。 たんぱく質とカルシウムが豊富。
- にんじんジャム。 チーズなどと合わせて食べる。
- 自家製チーズ。 脱脂粉乳から家庭で作る。
- 鮭。 焼いてほぐして野菜サラダと一緒にパンに乗せて食べたり、ご飯にはそのまま焼いて食べたりする。
- ひじき。 煮物にする。
- かぼちゃ。 煮物にする。
- 納豆。 畑の肉といわれる。 ネギや昆布のみじん切りをそえて。
- サラダ。 新鮮な野菜をたくさん刻む。
- たまねぎ。 スライスして、お湯にサッと通せば辛味がとれる。 サラダに入れてもよい。
- ドレッシング。 醤油、酢、ごま油を混ぜ合わせて中華風にすると風味よし。 これをサラダにかける。
以上が一汁十菜である。 「朝っぱらからそんなに沢山用意するヒマがあるわけなかろうにっ!」というクレームがつきそうだが、慌てちゃいけない。 上記のメニューから、2、3品選んで朝食とするわけである。 ある日はサラダにジャムにパンにホットミルク。 またある日は白いご飯に納豆、鮭、ひじきにわかめの味噌汁という風に。
なんだか、朝食を食ってみようという気になりませんでしたか?
※そうそう、オイのヨメがまた妊娠したのだそうな。 そんな唐突な。 ということで、身重のヨメには出産までまるべく休んでもらおうと思う。 あ、いつも休んでるか。
-参考文献:読むクスリ4-
人力車
人力車。
観光地でたまに見かける、大きい車輪が2つついた、人が引っ張って走る乗り物である。
発明者は和泉要助という人物で、開業したのは1870年(明治3年)だったらしい。
発明当初、「すばらしい交通機関」としてもてはやされた。
「今度発明された人力車という乗り物は恐ろしくスピードがでるので、乗っている人間のハラワタがグチャグチャになる。 なので乗車の際には生卵をひとつ抱えて乗り込み、黄身と白身がいっしょにならない程度の速度で走れば体に異常がない。」
など言われていたそうだ。
丸谷才一著 軽いつづらより
パリ流治療法
「コーラを飲みなさい。」
胃が痛いのは胃酸が胃壁の傷に染みているわけだから、それを中和する為にもコーラは適している。 さらにコーラは糖分が多いので、カロリーの補給にもなるからだとか。
パリに在住する日本人の男。 彼は風を引いて、38度の熱を出した。 病院へ行くと医師は言った。
「体温よりも2度低い風呂に入れなさい。 そして布団を掛けず、寒いところに寝かせなさい。」
日本のなるべく暖かくしなさいという療法とはまるで逆のことを言われて戸惑ったが、医師を信じて言われたとおりにすると、すぐ治ったそうな。
読むクスリ19より
ちなみにオイ家では昔から胃や腹が傷むと梅酢を飲まされ、風をひくと卵酒であります。
美味すぎてもダメ
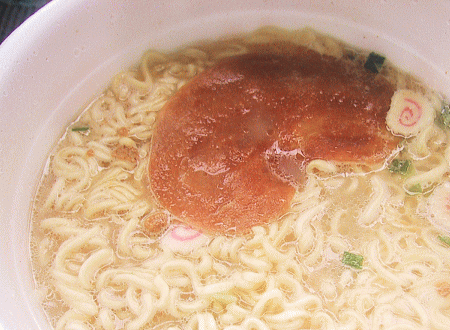
カップラーメンはウマイ。
コンビニなんかで新製品を目にするとほとんど買って食べてみる。 後乗せ式かやくだの、フタの上に置いて温めておいて、召し上がる直前にお入れくださいだの、「やけにコブクロがいっぱい入っていて、いちいち入れるのメンドクサイし。 全部一まとめにしろ。」なんて考えながら食うんだけど、昔と比べて随分美味くなってきた。
がしかし中には「正気かこれ?」なんて思う激マズカップメンなんていうのもチラホラ。 そこで今日はなんと、メーカーが美味しすぎる製品を発売しても売れないという日清食品部長の某氏のお話。
同社では試作品が出来ると下の肥えた社員がモニターになり試食をするのだそうだが、満場一致で「ウマイ! こりゃ売れるゾ! ウヒャ。」なんていう製品ほどダメなのだそうだ。
発売と同時にTVで大々的に宣伝をするわけだ。 そうしてそのCMをみた消費者達が試しに買ってみる。 「とりあえず買ってみよう」という試し買いのピークは発売から3週間目にくるとのこと。 7週目あたりになってリピート客「ウマカッタ。 もう一回買お。」という行動の波がくる。
発売前の試食でウマイと太鼓判を押された商品はこのあたりまではよく売れるとのこと。 7週目をすぎて売れ行きのカーブが上を向くか下を向くかが、カップメンの寿命を占うカギとなるらしい。 ヒット商品となるものはここから上昇カーブを描くわけだが、絶対売れる、といわれたものほどここから下降していくそうな。 そうして一旦下降を始めたら、いくら宣伝費をかけても回復しないという結果になる。
日清の会長、安藤桃福氏はこうおっしゃったそうな。
味がおいしすぎて、あるいは量がたっぷりとあって、十分満足すると、消費者に余韻が残ると。 口と腹の満足感が続く。 だから次に買おうと思うまでの時間が長くなる。 つまり2度目3度目のリピートにつながりにくくなる。
対して、「うーんウマイけどもうちょっとなんかこう・・。」とか、「ウマかったんだけど少ねぇーなコレ。」と、ある種の飢餓感を消費者に抱かせると、「次は満足できるかも。 よし。 もっかい買ってみよう。」と考えてリピートにはしる。 この積み重ねが爆発的なヒットにつながるというわけ。
つまり、「この値段ならばこの程度のお味でしょうな。」という消費者の中にいわるるひとつの尺度があるわけ。
-「読むクスリ」より-
口の肥えた飽食時代の消費者ではあるけれども、満足させすぎてはいけないと。 なるほどね。 でも消費者的には安かろう美味かろう量多かろうのほうが助かるよねウン。