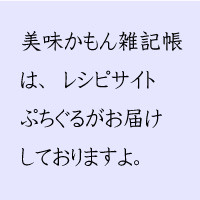鯨の給食再び

長崎市内の小学校給食で鯨が29年ぶりに復活したそうだ(4月のこと朝日新聞より)。
捕鯨が盛んだった頃の食文化を子供たちに伝えるのが狙いだそうで、近年調査捕鯨の拡大による鯨の市場価格の低下も追い風になってるのだとか。 給食でクジラが食えるなんて、実に、実にうらやましい。
最早給食を食べることは不可能だから、せめて毎日の食卓に一品鯨モノを出せるぐらいに、もう少し安くなってくれるとうれしいのだがムリか。 せっかく調査捕鯨拡大したんだから。
「昔は鯨は安かった」「昔くじらを食べ過ぎたのでもう食べたくない」このような話をいままで幾度となく先輩方に聞かされてきたわけだが、もしかすると今給食で食べてる小学生も、大人になったときに自分の子や孫にそういうのかもしれない。 いや、もしかするとこれ以降さらに調査捕鯨が拡大され、昔のように鯨が安くなっていくのかもしれない。 そうなると一体どういうことになるのか。 「鯨が給食に出されていたのを知らない世代」という言い方よりも「鯨が給食に出されなかった時代があったのだかつて」なんて言われるのかもしれない。
現在は鯨の価値が最高潮の時代であり、あと6、70年もすると、昔のように鯨食べ放題(だったのか)の時代がやってくるのかもしれない。 そう考えると、今という時代を生きねばならないオイその他鯨フリークは身がよじれる思いを死ぬまで持ち続けなければならず、死んでも死にきれないという話になってくるのではなかろうか。
東海林さだおさんが丸かじりにて「卵の美味しさは異常だ、皆安いから有難がっていないが、卵の美味しさからすると、もう少し値段が高くてもよいのではないか」というような話があったように記憶しているが、鯨の美味しさはどうであろうか。 値段と旨さのバランスはとれているのだろうか。 妥当にも思えるし、高すぎるようにも思えなくもない。
オイには夢がある。 鯨の各部位おおよそ食える部分全部(すえひろ、べーこん、赤身、オバ、さえずり、百尋、尾の身等)を目の前にズラリと並べ、いっぺんに、それを少しずつ味わいながら、チビチビ酒を飲むことである。 それには最低いくらぐらい必要なのかを、特売のベーコンをつまみながら少し考えた。
※この前寿司屋で鯨のあご肉の煮付けを食べた。 甘辛に煮付けてあり、どこか獣のにおいがした。
納豆 meets キムチ

今さらおおげさに語る必要はないが、納豆とキムチをあわせたものはうまい。 いや、キムチに納豆を混ぜ込んだものはウマイといったほうが適切か。 それとも日本人であることを考慮するならば、納豆にキムチを混ぜ込んだものと表現したほうがよいのかもしれん。
先日家族で焼肉屋に行ったときに、嫁が納豆キムチを注文して食べていたのを横からつまみ食いしてみたら、意外とうまかった。 それからここ最近、自宅で毎日納豆キムチを作って食べているだった。 納豆は包丁で叩いてひきわりにして、自家製のキムチが無い場合は、市販の、ちゃんと作られたキムチを使用して作る。 コチュジャンを入れてコクと辛味を追加するのも自由、胡麻油を少したらしてみたり、白ゴマを散らしてみるのも自由である。
ナチュラルチーズ:ミモレット

ハウステンボスをウロウロしていたらチーズ売り場を発見。 というか、チーズをあちこちで売ってる。 酒肴によさそうだな、とミモレットの切れ端を買って帰る。
薄く切ると、色姿が上等のカラスミとよく似ている。 食感は乾燥しすぎたからすみとよく似る。 なかなかよいつまみである。 もう少し大き目のを買えばよかった。
ウマいものを食べていると、必ずといってよいほど娘がトコトコと近づいてくる。 「動物的感」なのだろうか、オイが旨がっているのをいち早く察知するわけである。 「それなーに? からすみー?」
このミモレットは、娘にもからすみに見えるらしい。 ひとつまみ食べさせると、すごく嬉しそうな顔をした。 コストを考えると、カラスミをバクバク食われるよりも全然イイ。 ミモレット、常備しておこうか。
イカミサイル

オイは今、オニオンスープ作っている。 家族は風呂に入っている。
オニオンスープはタマネギを焦がさないように長時間炒めなければな らない。 こともあろうに50分とか焦がさぬように炒め続けなければならない。 よって鍋の前に付きっ切りで炒める作業に専念しなければならない。
何でか知らんがタマネギはほんのちょっと目を離しただけで焦げる。 さっきまであんなに美しいあめ色をしていたクセに、一瞬で鍋にこびりついて使い物にならないただの焦げたタマネギに変わり果てる。 カレーはおろか、何の料理にも使えやしない。
タマネギを炒め続けて30分が過ぎた頃、飽きてきた。 腹も減ってきた。 オイもひと風呂あびて、ビールをゴッゴッゴッとヤリたい。 このように考え始めたらその欲望はどんどん膨らんでいき、ついに缶ビールに手をかける。 プシュッ、ゴッゴッゴッ。
なんちゅうかこう、立ったままで、調理をしながらビールというのもなかなかよいものだね。 このビール、よく冷えているな。 おっと、タマネギが焦げちまう混ぜねば。 このようにしてタマネギを炒めながらビールを飲むと美味しいということを発見したオイは、テンションが上がってくる。 タマネギは段々とペースト状になりつつあるし、ビールはウマイし、もう言うことないね。 こんなことならば、屋外でタマネギを炒めればよかった。 外で飲むビールは格別である。 夕暮れの中、外でタマネギを炒めながらビールを飲んだらさぞ美味しかろう。 火の間近で熱い中、夕方の涼やかな風の中、ビールを飲んだらさぞ美味しかろうなー!
という様に、オニオンスープを作ることがオイに課せられた使命だったハズなのだが、いつのまにか、いかに美味しくビールを飲むかということに専念し始めた。
いまさら屋外でタマネギを炒めるわけにはいかんし、そうだ、ビールのつまみは何かないかな。 冷蔵庫をあさる。 うーん、キムチか、よしよし。 新しい缶ビールと、キムチを冷蔵庫から取り出し、ゴッゴッとやる。 ぷはぁー。 おっといけねえ、タマネギが焦げちまう。
うーん、なんちゅうか、もっとビールに合う油々した肴がほしいな。 なんかないかなあ。 うーん・・・・イカ!イカ発見! そうだった。 魚屋で活々としたヤリイカを買ってきてたんだった。 今日はヤリイカの刺身で日本酒を一杯と計画してたんだった。
このイカをタマネギの横っちょでバター炒めにしてビールを飲んだらさぞオイシカろう。 やってみっか! でもタマネギ炒めは最早大詰め。 火力は最小にし、絶えずかき混ぜている状態。 イカをさばく時間なんてねえな。 うーんどうすっか・・・まてよ、イカを丸ごと焼いてみたらどうだろうか?
ワタもスミもなにもかもつけたまま、丸ごと一匹のイカを鉄板焼きにしたら美味しいのではなかろうか。 鮎だって塩振って丸焼きにしたりするじゃないか。 日本人には焼き魚をむしって身と骨に分別するスキルが備わっているわけで、それに比べたら丸焼きのイカのトンビを取り出すことや、透明の甲を引っこ抜くなんてことはワケナイはずだ。 なんでイカの丸焼きってないんだろうか? バターと塩コショウと酒で、丸焼きの鉄板焼きにすればよいのである!
早速、タマネギの横っちょの空いてるコンロに鉄板を配置し、強火でガンガン熱する。 白煙が上がり始めた頃、目の前にタマネギを炒めるのに使ったバターが転がっていたのでそれをヒトカケラ放り込み、ヤリイカを丸ごとすべらせた。
「ジョワー」というウマソウな音がして、下足が縮れてくる。 すかさず目の前の塩コショウを振りかける。 バターの焦げた、いい香りがキッチン内に充満する。 「おぉー、これだこれ、ビールに合うぞー」と興奮し、ビールをあおる。
イカを一旦ひっくり返して焼いた後、元の位置に戻す。 仕上げに日本酒をイカの上からブッカケルと、ボワーっと炎があがった。 「ホッホッホッホ、ファイヤー!」とつい口ばしってしまう。

もうもうと立ち込める煙と、オイの奇声により一体なのが起きたのかと不安になった子供たち、嫁が風呂からでてきた。 そこで一同が見たものは、キッチンでタマネギを炒めつつ、イカから火柱を上げながらビール片手に狂喜乱舞しているオイの姿であった。 「それって火事になんないの? んで? オニオンスープは? まだ? あそ」という言葉を残し、一同風呂へと帰っていった。
イカは焼きすぎてはいけない。 そもそも刺身用のイカだし、生焼けだって平気なはずである。 程よく焼けたイカをエンペラのほうからほうばる。 こういうものは切って食べてはいけない。 かぶりつくのである。 イカの肉汁(肉汁でいいのか)が口中にほとばしり、頭の中につまっているイカのワタや卵の味が感じられる。 われながら絶妙の塩加減を施している。 胴体の途中で一旦噛み切った後、残る全ての部分をいっぺんに口に入れる。 美味しい。
イカの丸焼き大正解。 たまたま卵も入っていたものだからウマイの何の。 よく考えてみると、イカスミは料理に使うぐらいだから捨てずに食ったほうがよいのだ。 トンビだって干して串刺しにされ珍味として酒肴になったりもするし、とにかく、イカは丸ごと全部食えるということを実証したのである。 目だって魚の例をあげればおわかりいただけるであろう。 イカは捨てるところなんて皆無なのだ。
そうだな、せっかくなので、この簡単な料理に名前をつけたい。 烏賊の鉄砲焼きという料理がよく居酒屋なんかでだされるが、その名前の由来はよくわからない。 ゲソその他を胴体に詰め込んで焼くというところが鉄砲に弾をこめるところを連想させるからなのか、その姿が鉄砲玉のようだからなのか・・・・よくわからない。
そのへんから着想を得て、イカのミサイル焼きというのはどうであろうか。 見方によっちゃ、ミサイルにも見えないこともない。 ほら、下足がミサイルの噴出す白煙に見えないかい? なんだい、それならイカのロケット焼きでもよさそうじゃないか。
とにかく名前なんてどうでもよい。 美味けりゃいーのだ。 今日オニオンスープを作ってよかったよほんと。 あ、そういやタマネギ!
※2 叩き潰したニンニクをごま油で熱し、イカを焼き、紹興酒を振りかけて、コチュジャン、テンメンジャンで味付けするというもの試したが美味かった。
高野屋のからすみ

ようやく自家製カラスミ作りがひと段落ついた。 あとは食べるだけである。
餃子作りを趣味というか特技にしている人は意外に多く、数名の名がすぐに思い浮かぶ。 その中でもH氏のお宅へ、招かれた。
すでにおびただしい数の餃子が準備されており、まるで中国の兵馬俑のように、大皿に整然と並べられている。 ちなみにH氏の自家製餃子は餡のみが手作りで、皮は自作することはない。 「さあ、焼いちゃってよー」と餃子で飲み会スタート。
ウマイ。 時折カレー味やチーズ味の餃子にあたる。 それがH氏自慢の楽しみ餃子であり、それがたまたま当たった人の驚く顔を眺めながら一杯ヤルのがH氏のなによりもの楽しみなのだ。 なのでオイは、それらが当たったとき、本当は普通の餃子が一番美味しいと思っているにも関わらず
「うへぇ、カ、カレー味のギョウザですかー! おっモシロイですねーいやぁーしかし本当に。 まいっちゃうなホント。 ハハハ。」
と、冷蔵庫を購入するという話に過剰に反応するヤツを演じる某お笑い芸人のように、過激に反応してあげるのだ。
そうやって楽しい宴の最中、場を見計らって、懐から自家製唐墨を取り出す。 それを見たH氏は「オイくん、できてたんだー。 さ、早く切ってきて」と、オイ作からすみに過激に反応する。 H氏は、毎年からすみをあげてる人々のうちのひとりなのだ。 いそいで席を立ち、出来立てホヤホヤのからすみを切り分ける。
オイがカラスミをテーブルに出してから急に勢い付いたのが、同席していたこの付近の自治会長だとかいう年配の人物で、どうもカラスミに対して言いたいことがあるらしい。
その藤村俊二似の自治会長さんのコメントを以下に記す。
ほー、カラスミかね。(一口かじる) うんなかなかのものだね。 しかしこのからすみ、買うとどうしてあんなに高いのかね。私はね、カラスミには絶対金は払わないと決めているんだよ。 オイくん、カラスミの発祥を知っているかい? いやいや名前の由来ではなくて、どうやって日本で作られるようになったのか、だよ。
からすみはな、戦後、作られるようになったものだよ。 戦後まもなくは、原材料のボラがなかなか手に入らないことも多く、その希少性から高価なものだったのだが、現在はどうだ。 ボラはいくらでもいるのに、カラスミは高いというイメージだけで、べらぼうな値段をつけてやがる。
カラスミよりもウマイものなんていくらでもあるんだよ。 だからね、カラスミを高い金払って買うよりも、それと同じ金をだして、イイ肉でも買うんだよぼくは。
と、このように、自治会長はおっしゃる。 この話が真実なのか、そうでないのかはまったく気にする必要もないし、人それぞれの思いがあるだろうから「はぁ、そうなんですね」と返事をしただけだった。 この話の最中、自治会長氏はひたすらカラスミをつまみ続け、オイとH氏の食べる分がなくなったことも書き加えておこうか。
オイはカラスミが好きだ。 優雅な曲線で形作られ、適度にカチカチしていてなんだか玩具の性質を持ち合わせており、切ると美しいオレンジ色がまぶしく、つい懐に忍ばせたくなる。 自家製だって素晴らしいが、プロの手によるものは、尚いっそうのことである。
後日、オイは長崎の唐墨専門店「高野屋」に出向き、小さめのカラスミを購入してきた。 オイが自作しているものとは美しさが断然違い、風味もよかった。 こうやってプロの技に感動しつつ、来年の自家製カラスミ作りの糧とするのだ。
お年玉付年賀はがき2等当選毛ガニだカニ

「オイオイ、あたったよ!」
なんて興奮しながら近寄るヨメが言うには、お年玉付き年賀はがきで、2等に当選したのだという。
「2等って、何がもらえるんですかっ!」と、少し興奮してヨメに聞くと、地域特産品小包なのだという。 詳しい内容は、郵便局にいってみないとわからないのだとか。

郵便局から2等特産品一覧の載っているパンフレットを借りてきて、吟味する。 イロイロ美味しそうなものが載っているけど、どれにしようかな。 『そうめん』はいつも家に置いてあるしね。 『ステーキ』はなんだかサシの入り具合があやしいような気がする。 それほどでもないような気がする。 やっぱりカニかな。 毛ガニなんてなかなか自分で買って食ったりしないしさ。 松葉ガニよりも、やぱり毛のついている分だけ毛がににしようか。
待つこと10日ほどで、待望の毛がに到着。 ズッシリとしている割には小柄なカニである。 人間に例えると、タンクアボットのような短い手足。 柔らかい殻をはさみで切り進み、身を出して小皿にうつし、子供2人とヨメが食べる。 ナカナカ旨いのだとか。 アッというまにカニの身を食べつくし「早くちょうだいよ」とせかされる。 急いでカニをほじくる。
またたく間に毛ガニは食べつくされた。 オイは身を一口も食べなかったけれど、別に構わない。 殻にこびりついているカニミソを、あとでゆっくりとナメる魂胆なのだ。
この毛ガニ、実は2杯セットであり、残る1杯の毛ガニは、オイ家に2等当選の年賀状を送ってくれた張本人に送ることにした。
生牡蠣のテンコ盛り

長崎といえども2月といえばやはり寒いわけだがどうも今年は温かい。 なんだか冬を通り越して春が来たみたいだ。
今年、冬を感じられない原因としてもうひとつ考えられるのが、生牡蠣があまり売られていないということであろう。 毎年12月頃になると殻付きカキを買いまくり、毎日酒肴とするのだが、今年はさっぱり売られていない。
仕方がないので殻付きカキはあきらめて、スーパーにある剥き身のカキを探すがこれもあまり売られていない。 たまに目に付くと『特価!!生牡蠣パック2本入りで200円』なんていうありえないほどの安値で叩き売りされていたりする。
それを喜んで買い漁り、酒の肴とする。 もみじおろしをのせて小ネギを散らし、レモンを大量に絞り込んだポン酢でつまむ。 つるりとしていてミルキーでたまらん。 次々にパックを破り、生ガキを食う。 だんだんと飲みすすむうちに、カキをチョットずつ小鉢にだしてつまむことがめんどくさくなり、ザルに数パック分のカキをあけて、そのザルごと食卓へ運び、薬味を大量に加えたポン酢をチョンチョンとつけて食う。食う。
こんなウマいもの食わなきゃ損であると個人的に思うのであるが。
ヒラメの骨を見て思う

たまに行く飲み屋の座敷に、ヒラメの骨が飾ってある。 その骨はなんだか艶っぽく茶色に染まっており、木造の店の雰囲気によく合っている。 オイもちょっとマネしてみたいな。
「オヤジ、そのヒラメの骨、かっこよかですね。 どうやって作るんですかね?」たずねてみると、なんてことない。 ただ、ヒラメをおろして、その骨を換気扇の真下に一ヶ月程度干しておくだけなのだという。 そうして乾燥されたヒラメの骨は、乾燥したからなのか、店内のヤニや油を吸着したからなのだろうか、なんともいえないアジをかもしだしているのである。
オイ家ではヒラメの骨は味噌汁のダシとして活用するのが常であるが、せっかく乾燥ヒラメのレシピを聞いたことだし、試してみると、カンタンにできた。 もうちょっと干しておくと、ツヤがでてくるのかもしれん。
そして我が家で晩酌をしながら、壁にかけたヒラメの骨を眺めてみる。 我ながらよく出来てる。 いやぁー、しかし、こうしてみると、ヒラメってなんとも妙な姿をしている。 ペッタンコで海底にはいつくばっていることはさておき、なんちゅうかこう、もっと普通に、ペタンコになれなかったものかね。
『左ヒラメに右カレイ』という言葉が表すとおり、ヒラメの目は向かって左側にありカレイは逆。 ヒラメの例で言うと、左っかわに目が二つついているわけだ。 しかしよくよく見てみると、不気味だ。 2つの目のうち、上についているほうは、どう考えてもムリしてついている。 見るからに収まりが悪い形で目がついている。 本当は、もうちょっと下につくべきである。
それもそのハズ、ヒラメのペタンコになりかたはおかしい。 もっとこうカエルとか、サンショウウオとか、海で言えばアンコウとか、平べったい生き物というのはいるわけだが、みなそれぞれ、上から押しつぶされて扁平になったように、無理なくペタンコになっているという気がする。 ほらエイとか。 でもヒラメはどうだ。 たとえばアジが横になり、海底に沈んだ。 無論片方の目は海底側に接しているわけだ。 その状態が不便であるようでもあるが、居心地はよい。 もうしばらくこのまま横になっていようか。 と、現在の状況に甘んじているうちに、どうしても海底にいるほうがよくなり、そうして生きることに決めた。 でもエサを獲るためにはやはり両目で見ないと距離感がつかめなかったりするので、不便だ。 「ああ、神様。 どうか海底側の目を、反対側に移動することはできませんかね。」と祈り続けることン百年。 ついに願いは通じ、徐々に海底側の目が表側に移動してきた。
とこのように勝手に想像する。 であるからして、ひらめの目の付き方がおかしいというのは当たり前で、まだ進化している最中なのである。 あとン百年経つと、ヒラメの目は頭にたいしてちょうどよい位置に収まるに違いない。 しかしそこで安心してはいけない。 今度は口の付き方がおかしいという話になってくる。 今となれば元、ヒラメの右側面は、腹なわけであり、目もちゃんと定位置にある。 しかし口が横向いてるじゃないか。 上下に開く口ではなく、左右に開く口というのも不便だ。 いったいどうやってエサを食べているのかまったくもってあきれてものも言えない。 なにやってんだヒラメはよっ。
こうなれば一度全てを帳消しにすべきである。 ヒラメには海底から起き上がり、キチンと直立(でいいのか)してもらうべきである。 そして海底付近で若干泳いでいただきながら、片方に寄ってしまった目を元の位置に戻すように神様にお願いし、体の扁平をン百年かかってもン千年かかってもいいので普通の魚並に戻すべきである。 そしてアジ並の魚体に戻ったところで、再びペタンコへの道を目指してもらうべきである。 こう、縦につぶれてもらうわけだ。 すると骨格的にも、生活的にも安定し、豊かな海底ライフを満喫できるようになるのだと、一度ヒラメと話をしたい。 だってヒレとかもおかしいじゃないか。 内臓の位置とかetc。
とこのように、家族が寝静まる中一人酒をすると妄想がはじまる。 ヒラメってつくずく酒の肴になるヤツである。 もちろんこのヒラメの話はオイの脳が考えたものであり事実ではない。 さらに舌平目というヤツにちょっと文句があるという話はまた今度。
※その後このヒラメの骨は、家族から気持ちが悪いというクレームが寄せられ、多数決で取り外されることになった。
イカの黒作り@加賀百万石展

この真っ黒い物体はなんだと思いますか。
これはイカの塩辛なのだ。 イカの塩辛といえば普通のこような感じ→イカの塩辛
ビンに入っていなければ墨汁にしか見えないこれは、イカの墨入りの塩辛、人呼んで『イカの黒作り』というものである。
吉田健一著『旨いものはうまい』にこう書いてある。
烏賊の黒作りというものがあつて、これは烏賊の墨も一緒に混ぜた烏賊の塩辛であるが、義理にも綺麗などとは言へなくて、床に落ちてゐたりしたらもつと積極的に汚い感じがするに違ひない。 併し烏賊の塩辛はこれに限るので、見た目にはもつとお上品な、墨を取つてしまった普通の烏賊の塩辛はこれに遠く及ばない。
だとか。
長崎の浜屋百貨店で『老舗の味と技 加賀百万石展:1月16日(火)~22日(月)』なるものが開催されていて、そこで売られている和菓子を買いたいのだとか嫁がいうものだからついていく。 会場内をぶらぶらしていたところ、烏賊の黒作りを見つけたというわけ。
オイが購入した黒作りはホタルイカバージョンで、ホタルイカが丸ごと塩辛にされてあるというもの。 塩辛というぐらいだから、本来『辛い』はずの塩辛に、甘みがある。 これはイカスミによる甘さなのか、添加物による甘さなのかはわからんが、とにかく美味しいということだけは確かだ。
一瓶500円程度で、普通の烏賊バージョンもある。 お近くのイカ好きの方は、是非食べてみられることをオススメしたい。
クジラの切り落とし

以前熱く語ったクジラの切り落としが、また手に入った。 サエズリである。
ただ単に「切り落とし」というだけで妙に安くなるという制度に感謝しつつ、前々から試してみたかった白切肉のタレでクジラを食べてみると、やはりよく合う。
『ごあいさつ』
あけましておめでとうございます。 本年も、どうぞよろしくおねがいします。