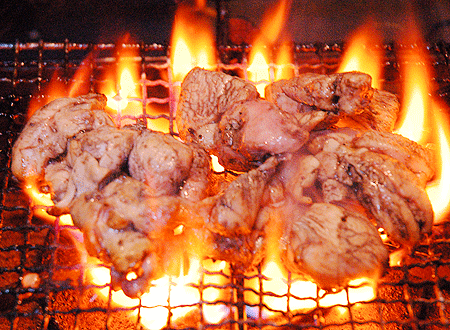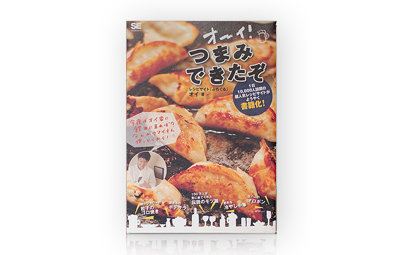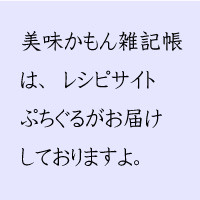高野屋のからすみ

ようやく自家製カラスミ作りがひと段落ついた。 あとは食べるだけである。
餃子作りを趣味というか特技にしている人は意外に多く、数名の名がすぐに思い浮かぶ。 その中でもH氏のお宅へ、招かれた。
すでにおびただしい数の餃子が準備されており、まるで中国の兵馬俑のように、大皿に整然と並べられている。 ちなみにH氏の自家製餃子は餡のみが手作りで、皮は自作することはない。 「さあ、焼いちゃってよー」と餃子で飲み会スタート。
ウマイ。 時折カレー味やチーズ味の餃子にあたる。 それがH氏自慢の楽しみ餃子であり、それがたまたま当たった人の驚く顔を眺めながら一杯ヤルのがH氏のなによりもの楽しみなのだ。 なのでオイは、それらが当たったとき、本当は普通の餃子が一番美味しいと思っているにも関わらず
「うへぇ、カ、カレー味のギョウザですかー! おっモシロイですねーいやぁーしかし本当に。 まいっちゃうなホント。 ハハハ。」
と、冷蔵庫を購入するという話に過剰に反応するヤツを演じる某お笑い芸人のように、過激に反応してあげるのだ。
そうやって楽しい宴の最中、場を見計らって、懐から自家製唐墨を取り出す。 それを見たH氏は「オイくん、できてたんだー。 さ、早く切ってきて」と、オイ作からすみに過激に反応する。 H氏は、毎年からすみをあげてる人々のうちのひとりなのだ。 いそいで席を立ち、出来立てホヤホヤのからすみを切り分ける。
オイがカラスミをテーブルに出してから急に勢い付いたのが、同席していたこの付近の自治会長だとかいう年配の人物で、どうもカラスミに対して言いたいことがあるらしい。
その藤村俊二似の自治会長さんのコメントを以下に記す。
ほー、カラスミかね。(一口かじる) うんなかなかのものだね。 しかしこのからすみ、買うとどうしてあんなに高いのかね。私はね、カラスミには絶対金は払わないと決めているんだよ。 オイくん、カラスミの発祥を知っているかい? いやいや名前の由来ではなくて、どうやって日本で作られるようになったのか、だよ。
からすみはな、戦後、作られるようになったものだよ。 戦後まもなくは、原材料のボラがなかなか手に入らないことも多く、その希少性から高価なものだったのだが、現在はどうだ。 ボラはいくらでもいるのに、カラスミは高いというイメージだけで、べらぼうな値段をつけてやがる。
カラスミよりもウマイものなんていくらでもあるんだよ。 だからね、カラスミを高い金払って買うよりも、それと同じ金をだして、イイ肉でも買うんだよぼくは。
と、このように、自治会長はおっしゃる。 この話が真実なのか、そうでないのかはまったく気にする必要もないし、人それぞれの思いがあるだろうから「はぁ、そうなんですね」と返事をしただけだった。 この話の最中、自治会長氏はひたすらカラスミをつまみ続け、オイとH氏の食べる分がなくなったことも書き加えておこうか。
オイはカラスミが好きだ。 優雅な曲線で形作られ、適度にカチカチしていてなんだか玩具の性質を持ち合わせており、切ると美しいオレンジ色がまぶしく、つい懐に忍ばせたくなる。 自家製だって素晴らしいが、プロの手によるものは、尚いっそうのことである。
後日、オイは長崎の唐墨専門店「高野屋」に出向き、小さめのカラスミを購入してきた。 オイが自作しているものとは美しさが断然違い、風味もよかった。 こうやってプロの技に感動しつつ、来年の自家製カラスミ作りの糧とするのだ。