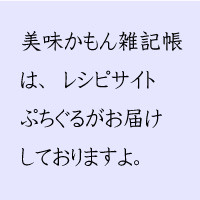白菜の古漬け

古漬けの作り方へ→
「そこの小道を入った所にあるらしいよ」
仄暗い路地を指差して彼は言った。 「へぇー。 で、美味しいの?」
「うん、アイツがいうにはナカナカな店だという話たけど」
なんでも彼の知人が偶然見つけた店なのだとか。
こぢんまりとした店の前に立ち、壁面に張り出されている品書きを眺める。 「ほぅ、イワシの刺身…何、女将自慢のシメサバときたか。 そーか、おでんの時期が来たんだなあ…覗いてみるか」
「ガラガラ…」「いらっしゃい」
真っ白な割烹着の女将さんが立っていた。 混んでいるが、幸いカウンターの隅っこがふたつ空いている。
ビールを飲みながら肴の注文を。 「とりあえずシメサバをお願いします」
女将:「ごめんなさいねぇ、今日は市場が休みだったから、シメサバ無いのよ。 刺盛りだったらなんとか作れるけど」
仕方ない。
「カキフライあります?」
女将:「なんとか一人前はできますよ。 あとはねえ、これといって今日は市場が休みなもので、たいした料理が作れないのよ。 おでんだったら沢山あるけどいかが?」
言われたとおりにする。
極めて家庭的な味のするおでんだった。 かえってそれが、うれしかった。 熱燗をもらう。
メニューに「漬物」とあったので、これも「おふくろの味」がするのかもしれんと注文した。
先のカキフライが出てきた。 小ぶりだからきっと地ガキなのだろう。 レモンを絞って口に放り込んだ。
「?」
今、口にしたのはカキフライである。 しかしこの味はカキでない。 まぎれもない魚の味だ。 でも相方がつまんだのは、まさにカキフイだったという。
目の前のカキフライをよく観察すると、微妙に形の違うフライが混じっていることがわかる。 それが、何かしら小魚のフライだったのだ。
「あのー、カキフライに混ざっている魚のフライは何なのでしょうか?」
女将:「ごめんなさいねえ、カキが残り少なかったから、ナントカという小魚のフライを一緒に盛り合わせたのよ」
な、なるほどですね…。
(more…)山葵から芽が
白里芋
野菜屋ですごい小さい里芋を発見。 一個が巨峰ぐらいの大きさで、何十個か入って一袋100円だった。 あまりの安さにつられて買ってしまう。
イカと煮たり、ともあえにしようとも考えたが、昆布だしで淡く煮ることにした。
里芋の入った袋を開けようとしたところで気づいた事は、この里芋が白里芋だということだった。 袋にそう書いてある。 白里芋なんていままで聞いたこともないし、ただの小ぶりな里芋が実は白里芋だったということだが、べつにどうだってよい。 どうみても小さいサトイモだ。
皮をむくときになり事の重大さに気づいた。 何十個もの小さいサトイモをチマチマとむいてしまわなければならないのだ。 およそ半数ぐらい皮をむいたところで飽きてしまったのだが投げ出すわけにはいかない。 こうなりゃもう意地だ。
むき終えたサトイモはさらに小さくなった。 柔らかく煮て大皿に盛り、食卓へのせておいた。 小さいからつまみやすいせいもあり、みるみるうちに少なくなってゆく。 たぶん2、3日は食べることができる分量だと考えていたのに、その日のうちに全部なくなってしまった。
小さいと子供ウケもよい。
山ワサビ
前に鮭児(たぶん)を頂いた某氏の所へ遊びに行ったら、また変わったものを入手してしまった。
ラップに包まれた白い物体を目の前に差し出しながら「何だと思う?」と某氏は尋ねる。
受け取り、そっと開いてみると細い大根のような切れ端が現れた。
「大根?いやもしかしてオイの捜し求めている朝鮮人参ですか?」
違う。 この物体は、山ワサビというものらしい。 ふーんワサビ。 どれどれ「ガリッ」
かじってみると、たしかにツンとくる。 でもワサビのそれではなく、なんちゅうかこう、すごく辛い大根といったかんじ。
山ワサビはホースラディッシュのことだ。 市販のチューブ入り練りワサビの原料は、このホースラディッシュなのだとか。 ローストビーフの付け合せにも使われるそうだ。
すりおろして刺身を食ってみる予定。
頂き物のグリンピース
ゴールデンウィークは過ぎ去った。 長男は小学校に行きたくてウズウズしているようだ。
勢いよく玄関を開け放ち、息子を送り出した。 玄関の脇に、グリンピースの山が。
もうそんな季節になったんだ。 近所の婆ちゃんが採れたてのグリンピースを早朝持ってきてくれたのだろう毎年のことだ。 そのままお礼に向かう。
朝から土鍋でグリンピースご飯を炊いた。 いつものように米を研ぎ、上からグリンピースを散らして炊き込んだ。 塩味をちょこっとつけた。
娘は大好物だ。 次男はおにぎりにして食べた。 長男はおかわりをした。 しみじみ素朴で正直な味がする。
レシピは後日ぷちぐるに追加する予定。
唐辛子
この季節になると近所のお婆さんから唐辛子の束をもらう。
ぶら下げておくとだいぶ日持ちがするからいろんな料理に活用する。
でも今回は、この束全部を使って保存食を作る予定。 それをお婆さんにおかえしするというわけだ。
ジャンボにんにく
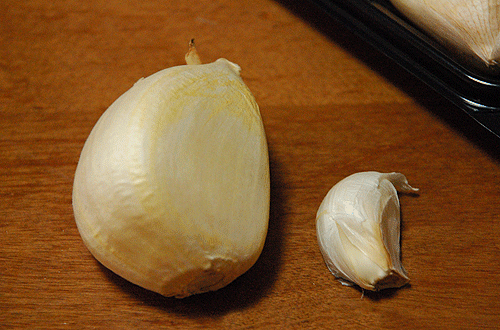
ひと月ばかり前だろうか。 夕方のニュース番組でジャンボにんにく販売開始!とかいうのが放送されていた。
「デカッ。」というそのままの感想を抱き、それきりジャンボにんにくの事を忘れかけようとしていた頃、スーパーでジャンボにんにくを見つける。
熊本産で、2粒入り200円弱。 パッケージには「エレファントガーリック」とも書かれている。 まずは購入してみないと。 普通のニンニクと比べてみると写真の通り。
さてジャンボにんにくで何を作ろうか。 ニンニクのしょうゆ漬けを作れば面白そうだなとか、丸ごと揚げてみようとか計画する。 せっかくジャンボなんだから、この大きさを生かした料理にしないと。
でもやっぱり、とりあえず生で食ってみないことには味がわからんだろう。 突如ジャンボにんにくの皮をむき、かじりついてみた。 間違いなくニンニクの味がした。 普段使うニンニクよりも大分汁気が多かったのは、新鮮だからなのか、それともジャンボだからなのか。 全部すりおろして、カツオのタタキを食った。
その他の野菜でもジャンボ版を作ったらどうか。 かぼちゃはものすごいのがあるし、大根も品種によってはデカいのがありそうだ。 そうだ、ジャンボタマネギがいいかもしれん。 1個で8個分ぐらいあるスイカの大玉のようなタマネギがあれば、カレーを作る際の手間が省けそうだ。
ジャンボワケギというのはどうだ。 筒切りにして、からりと揚げ、ネギリングで食べたりして。 いやどうせなら、元々小さいのをジャンボにしないと面白くない。 ゴマなんてどうだろう。
ジャンボ胡麻。 一粒がアボカドぐらいの大きさだったらインパクトがあるだろう。 炒ると大変危険な気がする。 丸のままかじりつくともはや「プチ」という食感ではあるまい。 このジャンボ胡麻を使って、胡麻ペーストを作ってみたい。
という風に、焼酎を飲みながらジャンボ妄想をしてみたが、妙案が思い浮かばなかった。
唐辛子の束ゲット
オイが住んでいる周辺は畑を持つ老人が多く住んでいる。
息子と2人散歩しながら今度の恐竜展にはいつ行くことにするか計画を練っていたところ「オーイ、オイ」と声がかかる。
道路脇を見上げると、太陽光を背に、やせた爺さんが立っていた。 S爺さんである。 このひとは数ある近所の畑のなかでも大々的に色んなものを作っておられる人物であり、収穫したものを季節ごとによく頂戴する。
この前はやさしい酸味のする柚子を沢山もらった。 その前は巨大な甘い、白菜だった。 そして今日は、唐辛子の束だった。
「軒先に吊るしておけーよう効くしぇん」ということらしい。
トマトのおでん
「トマトのおでん」と聞くとすこし驚いてしまうが、実際おでん種として存在するのだという。
その元祖は目白にある関西風おでん屋の「田のじ」らしいが、現在はコンビニのおでんにも見られるそうだ。
この話は東海林さだおさんの「コロッケの丸かじり」にあったもので、それをつい先日読み返し、早速作ってみようと思い立ったわけだ。 作り方といっても簡単。 まずいつものようにおでんを作る。 トマトが食べたくなったら、トマトのヘタをとり、反対側に十字に切れ目を入れて、おでんのツユの中に放り込む。 5分経過したらトマトを引き上げ、小鉢に盛り、トマトが半分隠れるぐらいにツユを入れる。 ただそれだけ。
トマトを何時間もグツグツ煮込むわけではないのだ。 なのでトマトにおでんの味は染み込んでいない。 皮はズルむけている。 見慣れない光景にすこしとまどいながらも、とりあえず箸でトマトを突き崩し、食べてみる。
アウ。
カツオ出汁と醤油で作ったおでんダシと、トマトの酸味、いやそれ自体の味が妙に合う。 なんでか? 聞くところによると、トマトは旨味成分であるグルタミン酸の濃度が非常に高いそうだ。
同じく昆布にもグルタミン酸が豊富に含まれており、カツオ出汁は昆布と鰹節でとったものであるからして、鰹節にはイノシン酸が含まれているわけだし、その両者が相見えると、素晴らしい相乗効果を発揮するとかいう話をラーメン作りの時に学んだような気がする。 とにかく、ウマイ。
東海林さんは全27冊に及ぶ(07/10/22現在)丸かじりシリーズで度々おでんのことを書いている。 「おでん」と題目のついたものをザッと調べてみると以下の通りだった。
鯛ヤキの丸かじり
- おでん屋襲撃:韓国ではなんでもかき混ぜて食べる。 ではおでん屋に…という話。
駅弁の丸かじり
- おでん革命:おでんのツユは和風ダシに醤油と決まっている。 が、このままでいいのかという話。
タケノコの丸かじり
- おでんをいじめる?:おでん食い方とか作り方がいじめるでどうとかいう話。
パンの耳の丸かじり
- 冷やしおでん見参:冷たいおでんの話。
おでんの丸かじり
- 「静岡のおでん」は…:静岡のおでんは串が…という話。
- 難物、おでんの袋もの:ためつ、すがめつ、袋ものを注文した男の観察記ほか。
パイナップルの丸かじり
- 自販機からおでん:秋葉原での話。
コロッケの丸かじり
- 韓国おでんの串は:新宿コリアンタウンで食べたデッカイおでんの串がどうのこうの…という話。
- トマトのおでん:この記事の話。
以上9題
このように東海林さんは再三にわたりおでんを語っておられる。 東海林さんのおでんに対する情熱が伝わってくる。 情熱は伝染する。 だからあなたもひとつトマトのおでんを実行してみるべきである。
※さらにこのあと東海林さんはコンソメスープでトマトを同じように煮てみたら美味しいということを発見し、飲んだあとのシメとして大いに期待できると書いておられる。 オイはまずはじめにごく普通におでんを楽しみ、中盤でトマトのおでんを食べて、あとに残るトマト色に染まったおでんダシに、色んな種を浸してトマト風味をプラスし、再びおでんを楽しむという食べ方が好きだ。
シイタケのバター焼き
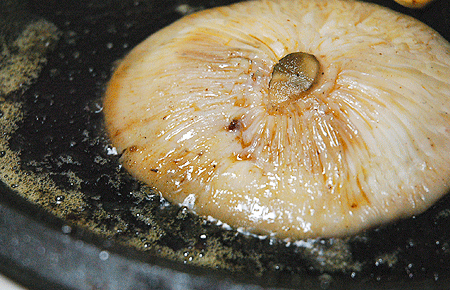
デカいシイタケを沢山もらった。
定年後、毎日家庭菜園に励んでいる近所のおじさんは、シイタケの他にもゴーヤ、ナス、キュウリ、キャベツ、白菜、トマト等、様々な野菜をほぼ無農薬で作っている。 そのおすそ分けを季節ごとに頂戴しているわけだ。
どの野菜もおじさんのまじめで実直な性格が現れていて、形がよく、そして美味しい。 オイはもらった野菜を料理にしてお返ししたりもするわけだ。

デカいシイタケは、バター焼きにして食べた。 鉄板にバターを多めに溶かし、石づきを取り除いたシイタケを放り込む。 そして塩コショウ少々。 ジャーとイイ音を出しながらバターはシイタケに染み込んでいきつつ、まろやかな香りを放つ。 傘の裏のヒダヒダの部分なんて、バターをたっぷりとかかえ込んでいる様子がうかがえる。 仕上げに今飲んでいる日本酒を少量『ジャッ』とかける。
熱々のところをほうばると、シイタケからバターがにじみ出てきてウマイなんてもんじゃねえ。 気が付くと、5つもシイタケを平らげていた。
キノコについて
キノコといえば、日本とか、東アジアでしか食されない食い物というイメージがありそうでもないが、実はヨーロッパ、アフリカ、アメリカと色んなところで食される。
日本ではキノコを『茸』なんて書くが、中国では『菌』と書き、さらにアメリカでは『muchroom(マッシュルーム)』、フランスでは『champignon(シャンピニオン)』という。
そんなキノコを学問的にいうと、食菌という部類にはいり、分類的には微生物になるのだという。 マツタケもシイタケもシメジもエノキもエリンギも、全て微生物なのだ。
微生物ったって、キノコは目に見えるじゃないか。 ぜんぜん『微』じゃないじゃないか! なんていう声も聞こえてきそうだが、待て。 キノコは目に見えないぐらい微細な胞子というのがその本体であり、その胞子から芽が出て、四方八方に伸びていく。 それが菌糸であり、菌糸がもつれあってキノコの形になる。 これを子実体というそうな。
なんでキノコはウマイのか? それは子実体の主成分がタンパク質であり、キノコが収穫された後、自己消化(自然に分解)してうまみ成分であるアミノ酸になるというわけだ。 さらに食べる際に唾液でもタンパク質が分解されてアミノ酸になるわけだから、ウマイに決まっているわけだ。
※さらに、キノコにはうまみ成分である『核酸』も多量に含まれている。 核酸がふくまれている食品としては、鰹節等が知られている。
キノコについては小泉武夫著:地球怪食紀行より