白菜の古漬け

古漬けの作り方へ→
「そこの小道を入った所にあるらしいよ」
仄暗い路地を指差して彼は言った。 「へぇー。 で、美味しいの?」
「うん、アイツがいうにはナカナカな店だという話たけど」
なんでも彼の知人が偶然見つけた店なのだとか。
こぢんまりとした店の前に立ち、壁面に張り出されている品書きを眺める。 「ほぅ、イワシの刺身…何、女将自慢のシメサバときたか。 そーか、おでんの時期が来たんだなあ…覗いてみるか」
「ガラガラ…」「いらっしゃい」
真っ白な割烹着の女将さんが立っていた。 混んでいるが、幸いカウンターの隅っこがふたつ空いている。
ビールを飲みながら肴の注文を。 「とりあえずシメサバをお願いします」
女将:「ごめんなさいねぇ、今日は市場が休みだったから、シメサバ無いのよ。 刺盛りだったらなんとか作れるけど」
仕方ない。
「カキフライあります?」
女将:「なんとか一人前はできますよ。 あとはねえ、これといって今日は市場が休みなもので、たいした料理が作れないのよ。 おでんだったら沢山あるけどいかが?」
言われたとおりにする。
極めて家庭的な味のするおでんだった。 かえってそれが、うれしかった。 熱燗をもらう。
メニューに「漬物」とあったので、これも「おふくろの味」がするのかもしれんと注文した。
先のカキフライが出てきた。 小ぶりだからきっと地ガキなのだろう。 レモンを絞って口に放り込んだ。
「?」
今、口にしたのはカキフライである。 しかしこの味はカキでない。 まぎれもない魚の味だ。 でも相方がつまんだのは、まさにカキフイだったという。
目の前のカキフライをよく観察すると、微妙に形の違うフライが混じっていることがわかる。 それが、何かしら小魚のフライだったのだ。
「あのー、カキフライに混ざっている魚のフライは何なのでしょうか?」
女将:「ごめんなさいねえ、カキが残り少なかったから、ナントカという小魚のフライを一緒に盛り合わせたのよ」
な、なるほどですね…。
漬物が到着。 白菜漬けである。 これからの季節、グンと美味しさを増す野菜だ。 ひとひら箸でつまみあげて口に入れた。
「?」
まるでキムチの古漬けのような、かすかな酸味がある。 いやこれはかすかどころではない、かなりの酸が、徐々に舌の上へ広がってゆく。 まるですぐきのようだ。 相方と顔を見合わせ、すっぱい白菜漬けをかみしめる。
これは、あえて酸味が出るまで漬けたものなのか、それとも単に、白菜漬けを置き過ぎただけのものなのかは判断できかねる。 ともあれ、はじめて口にした、酸味のある白菜漬けにしばしショックを受ける。
ヒソヒソすっぱい白菜について話し合っていたところ、となりの席に座る、耳にギラギラ光るピアスを2つはめたおじさんが話しかけてきた。
「これ、もうちょっと酸味が出てたほうがホントは旨いねんけどなあ」
だ、そうだ。
おじさんが言うには、もうちょっと重石をして寝かせ、少しスジスジさせたほうが良いのだとか。 なんでもこの方生まれが京都で、寒くなると母親が、一年分の白菜漬けを大樽で仕込んでいたそうで。 一年分とはいっても、翌年春になれば食べつくしてしまうわけで、その間は白菜の古漬けが待ち遠しくて仕方がなかったのだとか。
どうやって漬けるのかを聞けば、ただシンプルに塩で、洗い干しした白菜を漬け込むだけだという。 とにかく重石をしっかりとし、白菜が汁の中に常に浸っている状態をキープするのがコツらしい。
ここまで聞いておいて、白菜の古漬けを作ってみないわけにはいかない。 早速言われたように漬けて、毎日味見をした。 ちょうど六日目をすぎたころ、ほのかな酸味が醸し出てきた。
開封したての七味をふりかけてつまめば、ぬる燗をしんみり飲むことができた。
古漬けの作り方
白菜漬けが、ほのかに酸味を醸し出すまで安置しておけばよいだけです。

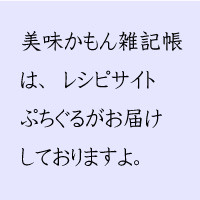



[…] 大量に白菜の古漬けをこしらえる。 […]