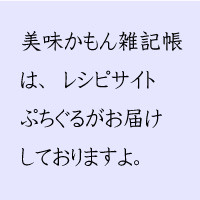店も水物

「あれ? こんな店だったっけ」
大好きだったあの店も、気が付けばなんか、前より居心地良くなく次第に足が遠のいて、ついに全く行かなくなる。 こういう経験をした事がある方も多いだろう。
以下最近の実例をふたつ。
そこまで出しゃばるか
燗酒専門店である。 珍しい業務形態だがいつもお店は賑わっている。 店主は酒に博識な上律義で人当たりも良く料理も旨い。
ところが近々、会話に割って入られる事が増えてきて、めんどうなので行かなくなった。
ビールの温度について
ビアバーで飲んだ、エビスがやけにぬるかったという話をしていた時の事である。
A氏:「さっきのビール、せっかくエビスだったのにヌルくて台無しだったよね」
B氏:「御意御意」
A氏:「やっぱこう『キーンッ!』とこなきゃビールでないね」
B氏:「御意御意」
突然店主:「かえってアロマが薫りませんでしたか? ビールは本来キンキンに冷やして飲むものではないのですシカジカ云々約5分・・・」
わかる。 おっしゃりたい事はよく分かる。 でもぬるいビールにゃガッカリする舌をもっているのでありますから、できれば聞き流しておいてもらいたい。
酒器について
次は酒器について語り合っている時だった。
A氏:「リーデルの大吟醸グラスって良いよね、飲み口がキリッとしてて、吟醸酒でも美味しくなる」
B氏:「ガラスの薄さが唇にちょうど良いものね!」
突然店主:「お燗の日本酒には、やっぱり盃しかありません。 口に近づけるにつれ香気が顔を覆いますから。 私達日本人は、昔貝殻を酒の器としていたから盃が生まれました。 一方ヨーロッパでは動物のツノを持って酒器としていたんですね。 だから足付きのワイングラスみたいなのが生まれました。 その国々に合った器が存在しているというワケであります」
勉強になった。 おっしゃりたい事はよく分かる。 でも、好きなんだものリーデルのグラスが。 盃も好きだけど、今リーデルに熱入れてんだから、できれば聞き流しておいてもらいたい。
日本酒の温度について
燗酒が続いているので、ちょっと冷たい酒が飲みたくて。
A氏:「冷酒ございますか?」
堂々たる店主:「ないんですぅー、ウチは燗酒専門店ですから。 そもそも日本には、酒を冷やして飲む文化はありませんでした。 それが冷蔵庫ができてからというもの、冷たい酒が出回るようになりました。 日本酒本来の味は、燗をしてはじめて活きるのです。 ところで冷や、つまり常温で飲む方法ならばお出ししております。 よろしければ冷やと燗、半々でお出ししてみましょうか?」
おっしゃる通りです、こちらで云う言葉ではないと反省しました、それではそろそろお会計を。

青筋も立たぬ
酔いも冷めるわ
数年来通っている焼き鳥と焼酎、日本酒が楽しめるお店である。 大好きな店だが、とにかく酒を注文しても店が空いていようが逆だろうが、まったく出てこない。
もはや「ワザとなのではなかろうか?」というくらい出ない。 2杯目が来るのに10分やそこら待つのなんてザラである。 もちろんホールスタッフがひとりしかいないワケではない。
結果注文していた焼き鳥は山積みになってしまう事となる、実に勿体ない。 酒飲みが串を口にする時はすなわち、酒がコップに入っている時だ。 こちらは焼き鳥で腹ごしらえをする為座っているのではない、酒を飲みに来ているのである。
書いとけよ
日本酒、焼酎共に、銘酒が沢山用意されている実に良い店だ。 しかし、通い始めて間もない頃から気づいてはいたが、店主はとにかく横柄な人物である。 それを重々承知していても通いたくなるほど良い店なのだがもう二度と足を運ぶことはない。
さんざん酌み交わしたあげく、最後の一杯に、これまで飲んだ事のない焼酎を注文した時の事である。 ちなみにこの店ではレア酒には「注文一杯まで」や「二杯まで」と記されており、もちろんその印がついている銘柄は、誰もが知る人気銘柄だ。
こちらとしては、それらの酒についてはこれまでさんざん飲んできたので目もくれず、無印の酒を注文するのが常である。 ところがレア酒の中に、見た事のない名の焼酎を見つけたのだった。 シメの酒にふさわしいと、張り切って注文した。
ところが出てきた酒は、これまでの一杯よりも明らかに分量が少ない。 この店でこのような事はかつて経験した事はない、ハテ?
「この焼酎、ちょっと少なくないですか?」 と、通りがかった店員さんに聞いてみた。 すると間をおかず現れた店主は鼻息荒く、こう言い放った。
店主:「この酒はとても貴重な酒だから普段90mlで出している所を60mlで出している(怒)! この酒を注文するのなら、そのくらいの事知ってから注文するんだな(怒)!」
聞いたことのない酒だから、飲んでみたかっただけである。 「注文一杯まで」のレア酒ですら無印と同じ量で出てくるのだから、この酒だって普通盛で出てくるのだと思っていて何ら不思議はない。
そう言うのなら、とても貴重な酒には印をつけて、分量が少なくなる旨をメニューに記しておけば良いでないか。 というよりも、そもそも店主と客という関係はさておき、人に対してその言いぐさは何だ、という話である。
この時我ら、あっけにとられはしたものの、不思議と腹は立たなかった。 そして酒には本当に申し訳ないが、ひと舐めもせずにそのまま会計を済ませ、店を出た。 もちろん別の店で楽しくシメ直したのは言うまでもない。