熱

三年前新宿での出来事。
出張二日目の朝、目を覚ますと体が鉛のように重たく、頭がマグマのように熱い……昨夜の酒が残っているのではないこれは、風邪だ風邪。 スマフォに手を伸ばし、近隣の病院を検索した。
地図を見ながら這うようにしてたどり着いたのは、かなり古びた、こう言っては申し訳ないが廃屋みたいな個人医院だった。
もちろん普段ならば別の所を探すが今はもう、生きているのがやっとであるほどツライ。 それにしても都会のど真ん中にこんな場所が存在しているなんてエモい。
薄く所々濁った、面が均一ではなくデコボコしているガラスの嵌められた、かすれた医院名が残る木の扉を引いて靴を脱いで「受付」と書かれた札の掛っている小窓へと歩いた。
そこには誰も居なかった。
見回しても患者もおらず、シンと静まり返っている。
「あのー、スイマセン。 診てもらいたいんのですが」
と声を投げればヒョイと顔を出したのは、白髪の痩せたお爺さんだった。
受付を済ませ診察室に促されてみれば、思った通り医者はさっきのお爺さんだった。 ワンオペである。
「随分辛そうだね。 熱冷ましをあげるから。 ところで長崎からは何をしに東京へ?」
「色々調べに来たんです」
「この近辺ならばあそこは行った? ガイドには乗っていないけど地元の人間としてお勧めするよ。 外観はさておき内部の構造がこうちょっと普通とは違う感じでねえ」
「先生…失礼ですが話を聞いているのも辛いくらいなんです。 なんとか早く処置を願います」
「そうかそうか。 熱冷ましを出しておくから、これを呑んで一日休んでいればすぐ治まるでしょう。 点滴をするというテもあるがね」
「点滴のほうが効くんですか?」
「うん。 普通飲み薬だとまず口から入って、胃を通って腸で吸収されて、それが体内に回っていくんだけど、点滴は薬を血管に直接注入するからね、効きが早いよ」
「ではそれでお願いします」
横になり、左そでをまくりあげてぐったり目を閉じる。 しばらくしてチクリとしたので目を開けば、点滴の袋がぶら下がっていた。
ポタポタ落ちる液体を見ていると、意識が朦朧として眠くなってきた。 具合が悪いながらも、寝に落ちる瞬間はなんとも心地良いものだ。 ひと眠りしていれば点滴も終わるだろう……グー。
「君は胃が強いほうかね!?」
突然の呼びかけに跳ね起きた。
「え、ええ弱くはないと思いますが」
「そうか、ならば胃薬は出さないでおくから。 薬の種類が多いと飲むのが面倒だからね」
「はい。 で、あと何分ぐらいかかりますかね点滴」
「そうだねえ、30分ぐらいかな。 急いでる? ならばもうちょっと早めに落とすようにしようかな」
と、先生は点滴が落ちる速度を速めた。 これまで「ポトリ…ポトリ…」だったのが「ポトトトトトォーッ!」とこれまで見た事のない速度で落ち始めた。
かなり不安になったので、念のために点滴の速度を速める事で何か弊害があるものなのかを聞いてみたところ、
「なに若いから大丈夫だと思う」
とのことだった。
少し腕がジンジンしびれる感じがしたが、10分程で点滴を終えた。
「薬を出すから」と先生は受付に回った。
薬は全部で五種類。 一度に飲む数、頻度、効能を薬袋の裏に4Bの鉛筆で手書きしながら、詳しく説明してくれた。 最後の二種については書く場所が無くなってしまったので、口頭での説明のみとなった。
受付の脇には古びた写真立てが置かれており、中にはセピア色の写真があった。 四十代程の女性がワンピースを着てポーズしている。 となりの花瓶には摘みたてみたいに鮮やかな黄色い花が一輪挿してあった。
翌朝熱は、嘘のように下がった。




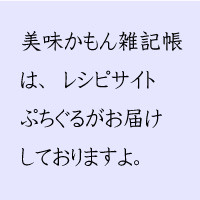

なんかほんのりと感動した!
映画見たかんじです!
古びかたにかなり味がありました。