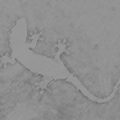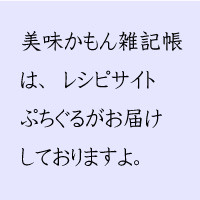どようび

窓の外を眺めながら熱々のコーヒーを飲んでいる。
風はほとんどない。 よくみると、雪がチラついている。 犬の散歩をしている人は、ニットキャップを被っているというよりも、頭全体を覆ってイイダコみたいになっている。 この調子では、また積もってしまうのではとぼんやり考えていると、キッチンのバナナと林檎が目についた。
林檎と雪。 この組み合わせがどこか気になりしばらくコーヒーカップを止めて考えた。
ああ、あの冬だ。
小学二三年の頃、長崎では考えられないような、やたらと雪が積もった日があった。 当然我らは喜んで土曜日の昼下がり、空き地にウソみたいに積もった雪で、巨大な雪だるまを建造中であった。
あまりにも長い時間転がしていたから、たぶん汗で湿ってきたのか毛糸の手袋がすこし気持ち悪くなり、いったん手をとめてパンパン雪を払っていた時の事だった。 階段の一番上に人が立っている。
ゆっくりこちらに向かって下りてくる彼は、一つ上の学年の宮内くんだった。
「オッスミヤウチくん。 雪だるまスゴイでしょう」
相変わらず彼は無表情だ。 学校でも目立つ生徒ではなく昼休みはいつもひとりで図書館にこもって図鑑を眺めているタイプの男子だ。
応答がないのでこれから先の雪だるま計画を話していたら、彼のジャンパーのポケットが、プックリふくらんでいる事に気がついた。
「それ何が入ってんの?」
彼は無言のままポケットのジッパーを下ろしておもむろにリンゴを取り出した。
「おやつ?」
と聞けば、昼ごはんだという。 我らは顔を見合わせてニヤつきながら「ミヤウチくん、リンゴ一個で昼ごはん足りるのかよ」とからかうように、やや上から目線でボヤついてみた。
すると彼はそのリンゴを左袖にゴシゴシこすりつけた後、とっさにカブりついた。
リンゴには綺麗なかじり跡が残っていた。
夕方家に帰り母親に、「あしたの昼ごはんはリンゴにしてよ」とお願いした。 「何アホな事言ってんの」と相手にされなかった。 そこでとにかくリンゴが食べたいので買ってくるようたのみこみ、あくる日の朝、待ちきれずに丸のままのリンゴにかじりついてみた。
とても固い。 皮が口に残ってやや渋く、噛んでいると甘酸っぱさが徐々に口の中へ広がっていった。
雪は止んだようだ。