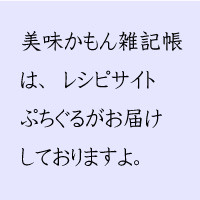4時間目

クラス一物静かなA君の周りに人だかりが。 「はてどうした?」と向かえばなんと!
定規の穴に人差し指を突っ込んでみたところ、抜けなくなっていた。
みんなは、それを助けようとゆっくり引いてみたり、押したりするも、がっちり指に食い込んでいて、抜ける気配がない。
将来宇宙飛行士を目指しているR君はこう言った。 「そうだ、セッケンをつけてみよう!」
A君を手洗い場へ連れてゆき、たんねんに指の周りへセッケンをこすりつけ、少々水でぬらして泡立てた。 そこで恐る恐る定規を回転させながら引っ張ると・・・・・・抜けない。
もはやA君の人差し指は紫色に変色しており、目には涙がにじんでいる。 「これはもう保健室に行くしかないね」という話にまとまり、みんなで向かう。
「アラーまたガッチリハマちゃってるね!」と、保健のセンセイはノンキな事を言う。
「どれどれ、センセイにまかせなさい!」と勢いよく定規を引っ張った瞬間、A君は「ギャッ!」と叫んだ。
「何してんだよセンセイ!」とみんな。 そこでセンセイはしばらく天井を眺めてから、「用務員さんからカナヅチを借りてきて」と、クラスで一番ワンパクなH君にお願いした。
「センセイこれでいい?!」と、アッという間に戻ってきた彼の両手には、センセイの想像していたモノよりも、はるかに巨大な、柄が長芋のように太く長いカナヅチが握られていた。
「こ、これしかなかったの?」とセンセイは目をむいたが、すぐに、まるで裁判官みたいに無表情で「じゃあA君、机の上に手を置きなさい」と命令した。
ふだん豆腐のように白いA君の顔はもはや、人差し指と同じくブドウみたいな色になっており、眉を「にわかせんぺいの面」みたいにズリ下げながらも恐る恐る疼く左手を置いた。
「Hクン、持つの手伝ってね、じゃ、行くわよ・・・セーの!」
「ゴォーン」
お寺の鐘をついたみたいな音が響いた。
ざんねんながらカナヅチは、A君の手と一体化している定規の上には降りず、コブシひとつはなれた所へ落ちた。 「テヘ!もう一回」と、まるでこの一大事を楽しんでいるかのように無責任な顔をしながらセンセイがカナヅチを持ち上げると、スチール製の机にはエクボができていた。
コツがつかめたのだろう、今度はH君の助けをかりずにセンセイはカナヅチを振った。 「バキリ」というなさけない音をたてて、定規は割れた。
A君の人差し指には、まるでそこから切りはなせるのではないかという程、深いミゾが刻まれていた。 指をさすりながら「ありがとうございます」と泣くようにつぶやいた。
「困った事があったらまたいつでも来なさいね!」というセンセイの呼びかけには、誰ひとり返事をしなかった五年二組の面々だった。