かつおの天ぱく

どしゃ降りの中向かったのは、三重県志摩市大王町。
ここに古式製法でカツオブシを造る名人がいるという。 切り立った崖の上に燻し小屋はあった。 眼前に広がる太平洋は、なじみの海とは違う。 巨大なうねりに圧倒されてボー然と、ただ砕け散る波を見おろしていたところ、「今日はまだ静かなほうです」と天白氏は現れた。

堂々たる体躯に鋭い眼光。 一瞬、作り笑いも出ないほどたじろいだが、いざ話をすると物腰の柔らかい紳士だった。 かつおの天ぱく代表取締役 天白 幸明氏である。
カツオブシは、カツオの身を蒸し、炙り、干し固めたもの。 これを天ぱくでは、「手火山式」で造っている。 「て、てかざん?」
「てびやま」と読む。 カンタンに言うと直火で燻す手法であり、現在も手火山式をとっているメーカーは全国でも数えるほどしか残っていない。

いぶし納屋に入ると、ウバメカシの香気に包まれた。 ついウットリしてしまうのは日々嗜んでいる燻製のせいもあるだろう。

薪を焚いた炉の上に、畳大のセイロが何段も積まれている。 中には黒光りするカツオブシが整然と並んでおり、焙乾することで、カツオの水分を徐々に抜いていく。

焙乾を繰り返し、固くしまったものを荒節という。

ちなみにオイは、この荒節でとった野趣あふれるダシが好きで、うどんのツユにはこれしかないと思っている。

この荒節の表面を削ってカビをつけ、天日に干したものが枯節。 カビづけ納屋の戸を引くと、枯節がうずたかく積まれていた。

年季を感じさせる土壁は、ワラがあらわになっているが、これをむやみに新築するわけにはいかない。 土壁には、その納屋特有の菌がおり、それがその店の味を醸す。
仮に土壁を作り直したとして、新しい菌がつくまでには最低三年が必要となるが、味噌蔵等でも新築すると味が変わってしまう為、老舗ほど古い建屋を大切にしている。 かつて建て替えの話も出たが、天白氏は断固それを拒んだ。

「飲んでみません?」と現れたのは天白氏の奥様。 「天」の字が記された猪口に入っていたのは、燗酒ではなく引きたての出汁であり、含んでみると濃い口なのに、臭みがまったく無い不思議。 ※余談であるが「天」の文字は天白氏直筆であり、白い器に天とだけ書き、天白と読ませている。

「今いただいたのは、どれですか?」しばし一角に並ぶ商品の説明を受ける。 それぞれ持ち味のある、天白渾身の出汁達。 そもそも氏が跡を継ぐと決めたのには、一枚の古い番付表があった。

江戸時代、すでに庶民は諸国カツオブシの番付表を作るほどに舌が肥えていた。 それをしげしげ眺めていた氏は、行司の欄に「志摩 波切節」の文字を見つける。 「全国のカツオブシランキングを取り仕切る役にあった波切節は、きっと凄い高品質だったと思うんです」

では、どうしてその頃から三重県のカツオブシは名が通っていたのだろうか? 一般に焼津、枕崎がメッカだと言われるが、そもそもカツオブシのルーツは和歌山沿岸、三重県沿岸部にあるらしい。
古くは干物や生節の状態が主であったが、平城京、平安京、伊勢神宮に奉納するには生では日持ちしない事から「燻す」技術が生まれた。
そしてある時三重の漁師が遭難漂流し、たまたま高知に流れ着いた。 そこで世話をしてもらった礼にと、燻しの技術を伝授した。 やがてそれが九州へと広がっていったという。
昭和初期、三重県には母屋と一緒になったいぶし小屋が200件あった。 それが今では3件だけ。 真珠養殖技術が発達した折、皆それに移行したらしい。

「うちはそれに乗り遅れちゃってね」
なんて笑う氏だが、聞かせていただいた想いからするに、目先の利益を追うのではなく、伊勢志摩の文化を守り伝承する事こそが己の使命だと考えているのだろう。

笑顔が素敵な天白氏。 手に持っているのはノベルティのトートバッグで、 趣のある招き猫とカツオブシの画は、版画家 徳力富吉郎さんのもの。 かつおの天ぱくのパッケージにもふんだんに徳力氏の画が用いられている。

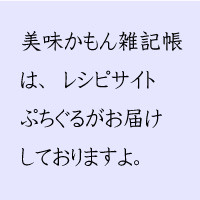


待ちに待った鰹節紀行、さすが素晴らしいです。古いものを守る事って本当に大切ですね。またオイさんの写真と解説を見ていると鰹の香りがここまで漂ってきそうでした。天白さん、お元気でお仕事続けてくださる事を祈ります。
[…] 天白社長におかげ横丁を隅々案内してもらい、では次に移動しようとしたところで「おっとこれ忘れたらあかん」と連れていってもらったのが赤福本店。 […]