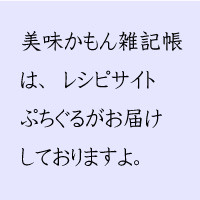『舌鼓ところどころ』吉田 健一
卓袱
御鰭と呼ばれるのは、客一人に就て鯛を一尾使った証拠に、椀毎に鯛の鰭を二つずつ付けるからだそうで、客が先ずこの鰭を取り除けて宴会が始る。
卓袱料理はもともとが一種の家庭料理で、今日でも長崎で客に家で御馳走する時はこの方式に従うことが多いそうであり、~中略~
銘々が小皿に料理を取り分けるのに、箸は返さないことになっていて、小皿が一人に就て二つしかないのは、小皿に取ったものは全部食べてしまえということになる。 だから、酒を浴びるように飲んでも、二日酔いはしない訳である。~中略~
卓袱料理を考えた人間はやはり酒飲みだったのに違いない。
角煮
脂っこいのに、それが滋味に感じられるだけで、一つ食べることがもう一つ食べる気持ちを誘う。 どちらかと言えば甘い煮方なのが、この場合も酒を辛くするのに丁度いい程度で、本当を言えば、これを皿に盛ったのと酒があれば、それだけで充分な御馳走である。 これを十一食べた先輩がいるという話も聞いたが、無理もないことだと思う。 消化はいいのに決まっているし、要するに、幾らでも食べられて、翌日、又食べられるのがこの豚の角煮である。
アラ
身を湯引きしたのの他に、腸、鰓、それから皮をやはり湯引きしたのが出た。 ちり酢で食べるので、この魚は初めはただやたらに旨いものだということしか解らない。
それ程、他のどんな魚とも違っていて、河豚に似ているが、河豚よりも軽いし、身が恐ろしく引き締まっているのが、何かの軟骨を食べている感じで、その軟骨に味があるのだから、少しは興奮するに足りる。
そう言えば、腸も、鰓も、それから殊に旨い皮も、この軟骨の歯触りで、それが凡て身とともに或る何か微妙な味で統一されているから、一度食べれば忘れることが出来ない。
吸いものにも、味噌汁にもなり、ちり酢の代わりに酢味噌でも食べられる。
鯨
とろの所を薄く刺身に切って生薑醤油で食べるのは、鮪のとろよりも旨いようで、山葵の代わりに生薑を使うのは鯨が哺乳類であることを尊重してなのだろうか、そう言えば、どこかロオスト・ビイフの焼き過ぎないのに似ていて、ブルゴオニュの赤葡萄酒と食べても合うかも知れない。
唐墨
長崎の唐墨は干し柿を思い出す位肥えている。
水貝
これは恐らく世界の料理の中で最も固いもので、併し御馳走には違いない。 その匂いにも、味にも海が染み込んでいる。
鰰
最後に運ばれて来たのが鰰の湯上げという料理だった。 これは湯豆腐の豆腐の代わりに鰰を使ってものと思えばよくて、それ故に勿論、昆布だしである。 ~中略~
その肉も上等の鱈を思わせて旨い。 但しどんなことがあっても逃してはならないのは、身と一緒に土鍋の中で煮えている鰰の白子で、これは世界の御馳走の一つに数えて構わないものの中に入る。 又それだけ、その味を説明するのは困難であるが、強いて言えば、酒田に出掛ける前に邱永漢氏のお宅に招かれて、食事の最後に出た扁桃の実を摺って作ったスウプの滑らかな舌触りがこの鰰の白子に一番よく似ていた。
河豚の糠漬け
河豚の糠漬けは河豚の半身をまるごと漬けたのを、糠を落としてなるべく薄く切って出すので、それがどういうのか、上等の牛肉を焼いたのを薄く切った時の味がする。 金沢では河豚の刺身は食べないらしいが、その刺身が幾らでも食べられるのと同じで、この糠漬けで飲み出したら、適当な辛さもあって、切りがない。 併し金沢では鰯も鯡も糠漬けにして、この三つのうちでは鰯の糠漬けをそのまま食べるのが一番旨い。 これも鰯の脂のせいかどうか知らないが、それが脂っこい代りにこの糠漬けの味は変わった感じで、やはり何か木の実を食べている時の満足した気持ちにさせてくれる。 鯡の糠漬けは酢で食べて、その粕漬けや、河豚の粕漬けもあり、これは誰にも高級な印象を与える酒の肴である。
菓子
岩永商店
磨屋町の岩永商店で作っている寒菊という菓子は餅に砂糖と水飴を混ぜたのを搗(つ)いて固く焼き、上から白砂糖を掛けたもので、昔あったラスクという菓子の味に似ているのが懐かしかった。
榎純正堂
浜名町の榎純正堂の一口香(いっこっこう)は有名である。 見た所は小型の饅頭であるが、固く焼いた皮の中は空洞になっていて、皮の内部に蜂蜜が付いている。 これで結局は、麦粉と蜂蜜の味で、これならばビイルの肴にもなるのではないかと、妙なことを考えた。
福砂屋
船大工の福砂屋に寄った序でに、工場を見せて貰ったのは幸だった。 カステラは規格に合って市場に出されるものよりも、何かの拍子に焼き損って撥ねられたものの方が、保存が利かないだけで、ずっと芳しくてねっとりしていることが、店で出されて解り、それで帰ろうと思っていると工場に案内されて、カステラを焼いた後で型にくっついている粕を削り取って食べると、この方が焼き損ないよりも更に上等だった。 あれが一罐手に入ったら儲けものであるが、店から外へは出さない。
あとがき
そしてこの著者は、食べものの味のよさを言うのに「うまい」(著者は旨いと書く)という賞めことばを使い、決して、「おいしい」ということばを使わない。 この本の中には「おいしい」という語は一つも出て来ていない。 これも著者の生育の時代を示すことであって、かつて「おいしい」は女ことばであって、男は使わなかったのである。 こういう、用語のはしばしにも、おろそかでない文章表現がうかがわれる。