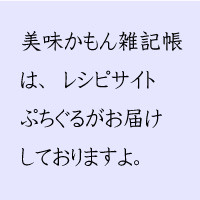薄田 泣菫 『茶話』
薄田 泣菫の『茶話』を読み終えた。
茶話は大正末期から昭和にかけて、毎日新聞に掲載されていたコラムであり、当時の毎日新聞は、この茶話だけで売れていたと、開高 健が『知的な痴的な教養講座』に書いている。
今回読んだものは、昭和三年に創元社が出した『茶話抄』に収録された著者自選の154篇を再録したというもの。
丸谷才一は、薄田 泣菫について次のように語った。
泣菫は例のコラムニストのはしりなわけだが、 しかしこんな紹介の仕方をしたせいで、後世の猥雑なコラムと同一視されては気の毒だから、 一つ見本を出してみよう(「俳諧師の頓智」を引く)。
泣菫は、知的であることと暖かい肌合いとが一致しており、イメージの使い方がじつに巧妙だ、と評している。
その「イメージの使い方」について、解説の坪内祐三はこう書いている。
イメージと言えば、『茶話』を一読した読者は、泣菫が人間を動物にたとえる比喩表現に巧みなことに気づくだろう。 そしてその比喩が独特のユーモアをかもし出していることも。
読んでいて気になった表現を以下列記。
- 石のような四角い、そしてまた石のような厳粛な顔に、急に石のような冷たさが現れて来た。
- 若い将校は、腹の減った狗が主人の顔を見る折のような狡そうな眼つきをした。
- 小説家は血だらけな牛の肉を噛み馴れた口もとを子供のように窄めながら言った。
- 鞴のような音をさせて、すうと深い溜息をついた。
- 和尚は木の株のような頭をふった。
- 橙のように円い小さな顔は、靴墨で真黒に汚れていた。
- 将軍の顔は、悲しさと腹立たしさとで、壊れた弁当箱のように歪んでいた。
- ベンシャミン・フランクリンが、ある冬馬に騎って田舎に旅行をした事があった。 雪の多い頃で夕方田舎の旅籠屋に着いた頃には、馬も人も砂糖の塊のように真白になっていた。
- 老女は石のように冷たそうな顔をあげた。
- 政宗はお産でもするかのように、蟹のような顔をしかめてうんうんとうなっていたが、
- いずれも腹の減ったような笑い方だった。
- マリイ・アンチンの円い顔は銀貨のように真青になった。
- 馬の上で左衛門尉の二つの眼が蝋燭のように光っていた。
- 狼のように黙って死にたい。
実に愉快で、その光景が目に浮かんでくる表現だ。
茶話を読んでいて時折、「えっ?オチは?」という一篇に出くわす時がある。 だが読み進むうち、面白い話の中に時折現れるその「オチは?」と問いたくなる一篇が待ち遠しくなってくるのだ。 つまりこれは、「茶話特有の曖昧すぎるオチ」にハマりはじめたことを意味する。
最後に・・・どの一篇にしようかしばらく悩んだが、お気に入りの話をひとつ引いておく。
天文学者
サア・ロバアト・ボオルといえば、愛蘭(アイルランド)生まれの名高い天文学者で、剣橋(ケンブリッジ)大学でその方の講座を受持っている先生だが、幾ら天文学者だからといって、木星から高い生活費を受取る訳にもいかないので、昼飯は精々手軽なところで済ませる事にきめている。
ある時、久振りに旧い友達が訪ねて来たので、天文学者は滅多に往きつけない土地一番の料理屋に連立って往った。 そして初めから終いまで彗星の談話をしながら、肉汁を飲んだり、ビフテキを齧ったりした。 すべて学者というものは、自分の専門の談話をしなければ、どんな料理を食べても、それを美味いと思う事の出来ないものなのだ。
料理が済むと、主婦は勘定書を持ち出した。 天文学者はじっとその〆高を見ていたが、暫くすると望遠鏡を覗く折のように、変な眼つきをして主婦を見返った。
「主婦(おかみ)さん、僕はここでちょっと天文学の講釈をするがね。 凡てこの世界にある物は、二千五百万年経つと、また元々通りに還って来るという事になっている。 してみると、僕も二千五百万年後には、やはり今のようにお前さんの店で午飯を食っているはずなのだ。 ところで物は相談だが、この勘定をそれまで掛にしておいてはくれまいかね。」
「ええ、ええ、よござんすとも。」と主婦は愛想笑いをしながら言った。 「忘れもしません。」ちょうど今から二千五百万年前にも、旦那は今日のように、手前どもの店でお午飯を召し食って下さいましたが、その折のお勘定が唯今戴けますなら、今日のはこの次までお待ち致しましょう。」
天文学者は呆気に取られて、笑いながら銭入を取り出して勘定を払った。 なるほど銭入を見ると、二千五百万年も前から持ち古して来たらしい、手垢のにじんだものであった。