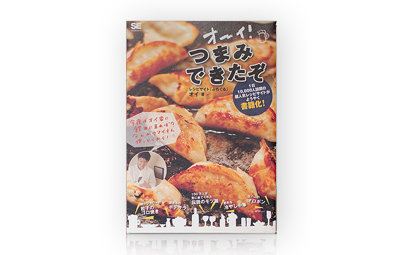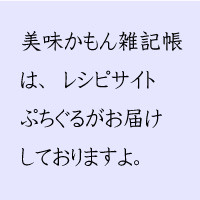萩焼で酒が旨くなる

三代続く、竹職人さんの手があまりにも魅力的だったので、会話をしながら凝視してたんです。 そしたらご本人が「見てるだけじゃわかりませんよ。 さ、握手しましょう!」と言われたので「シメタ!」とばかり勇んで手を差し出しましてね。
そうですねえ「人の手」を握っているというよりも「イセエビ」をつかんでいる感覚に近かったですね。 普通だと、そこに突起なぞあるはずのない部分がゴツゴツ隆起したつまりタコになっており、すぐさま握手を解いて、手のひらを両手でつかんでしげしげ観察させていただいたのでした。
この無骨な手が生み出す繊細な竹細工・・・作品だけでなく、作り手さんと合わせて鑑賞すると、感動は三倍になります。
さてその足で、てどの足だ! となりますよね急に言われても。 伝統工芸展に行ってたんですよね。 そしたらもう観たいものばかりで一日では回りきれずに途方にくれたというワケでして。
もちろん買い物もしましたよ、竹細工の櫛に真珠、そして自分用にはやっぱり酒器です、 この無骨な萩焼のぐい飲みには惚れましたね。
頃良い大きさ、野趣あふれる釉ヒビ。 使うのがもったいないくらいですが、萩焼の大きな特徴に、使っているうち刻々と変化してゆく肌質があります。
これなんざ言ってみればまだ未完成品であり、「萩の七化け」を堪能するためには使いまくらにゃなりません。 呑んで旨し、見て愛しな萩焼なのでした。

萩焼とは
古くから陶芸のさかんだった山口萩に、今日の萩焼が誕生したのは慶長十年といわれます。
萩焼の良さは、吸水性です。 それは地土のあまさに由来しますが、これが使い続けるうちに萩の七変化を生み出す基となります。 表面釉薬のヒビ(貫入)に茶渋が入り、得も言われぬ表情が生まれるというわけです。