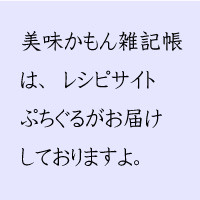カキ氷屋さんになる

子供らが通う保育園で、夏祭りが開催されるという。
手伝える保護者は、なんかやってくださいというので、逆になにを手伝えばよいのかを聞いてみると、カキ氷屋さんなんてどう? といわれた。
おーあれ前から一度やってみたかったんですよオイ。 と、二つ返事で引き受け、人生初の、カキ氷屋さんとして、デビューしたわけである。
一杯150円。 イチゴ味と、メロン味があり、お金を払った人には、どちらかを選ぶ権利がある。 肝腎なカキ氷を作り出す道具は、オイ個人的には、手動式の、なんだかレトロな手回し式のヤツでシャリシャリとやってみたかったんだが、そんなもの、今はどこにも現存していないのだとか。 よって電動式の、なんだか味気ない機械から、カキ氷が排出される。
2、3回売ったら、調子がでてきた。 「ハイラッシャイ、ラッシャイ。 ん?イチゴ味ねキミは。 そうね。 きみはなんだかハキハキしているな、気に入ったよオイは。 じゃ、ちょっとサービスしておくけんね。 ドボドボ。」
と、来る客来る客に、氷本体と、シロップを大盤振る舞いしていたら、背後から冷たい視線。 恐る恐る振り返ると、見ていたのである。 保育士さんが。 「オイくん、あんたやりすぎ。 もうちょい考えながら、販売してくださいよ。 ふんとにもう、チッ。」という無言のプレッシャーを感じたオイは、若干反省して、カキ氷を取り決め通りの分量にて販売することにしたのである。
でもこれじゃ少ねぇよ。 ケチケチすんなよ。 祭りだぞ、祭り。 なんて思いもするが、なんでもこの夜店の利益が、園児たちの活動を支える大事な手助けになるという話を聞いて、心で泣きながら、子供達や、その親たちに、少ないカキ氷を販売し続けたのである。
とまあカキ氷屋さんに熱中しているうちに、あたりはいつのまにか暗くなり、太鼓の音と、おばちゃんたちの歌声を聞きながらしばらくボーッと、したのである。 どうも、リガタンシタ。