日本刀の作り方

熱量
鉄を自由に扱うには高温の熱が必要である。
西洋には早くからコークスがあり、1800℃の熱が出せたが、日本には木炭しかなく、いくら酸素を送っても1200℃が限界だった。
しかし、鉄の溶解点は1800℃で、木炭をふいごで吹いて、いくらがんばってもせいぜい「アメ状」になるのが精一杯だった。
鋼鉄は、砂鉄を原料にして作る。 砂鉄粉を石英粉と、木炭粉と交互に重ね、溶鉱炉の中に入れる。
三日三晩熱すると、どろどろのアメができる。 もし1800℃出せればここで鋼鉄ができ、あとは鋳型に流し込めば終わりだが1200℃しか出せないからアメ状の物質には不純物が沢山入っている。
そこで不純物を取り除いて、固めると銑鉄ができる。 それを叩いて細かくし、さらに石英粉と木炭粉をまぜて溶かすと、玉鋼(たまこがね)ができる。
玉鋼

玉鋼は炭素分が多く、固いがモロい。 これに柔軟性を与える必要があるので、再び溶鉱炉で半溶解にして叩いて鍛える。 すると炭素が火花という形で放出される。 この叩き方が重要で、初めから終わりまで叩く力が均等でなければならない熟練を要する作業である。
鍛造する

叩いて火花を飛ばせば飛ばす程、鋼鉄の鉄分の純度は高くなるが、炭素を出し切ってしまうと、グニャグニャのバネになってしまうので、ある一定の限度で叩くことをやめる。 こうして出来上がるのが日本刀の芯である。
これそのままでは刃物としては弱い。 なので表面に硬度の高い鋼鉄を付けてよく熱し打ち固める。 次に刃の部分に焼きを入れてここだけ最も硬度が高くなるようにし、研いだ時よく切れるようにする。 それには、全体に粘土を塗り、刃の部分だけそれを落として火に入れる。
焼いたものを生ぬるい水につける。 すると刃の部分だけが密度を増し、非常に硬質な刃物になる。 粘土に包まれたその他の部分は柔軟性を残したままで、一本の刀が固さと柔らかさという相反する性質を持つようになる。
ここで重要なのが水の温度で、冷たすぎると収縮が早く起こりすぎて刃自体にヒビが入ってしまうし、温度が高いと硬度が得られない(今日では一般的に7℃から13℃と言われている)。
(梅干と日本刀 上より)
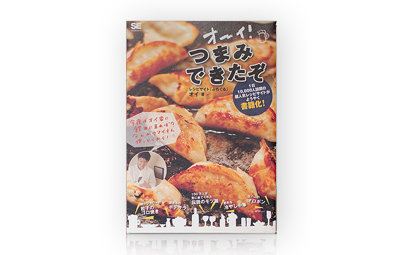
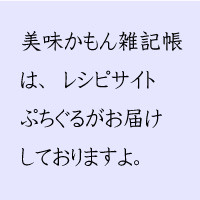



[…] うなのである→日本刀の作り方。 […]