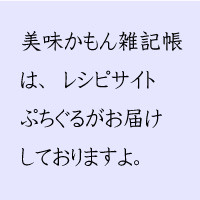金持ちの隣で飲む酒はメンドクサ旨い
携帯電話でメールを打つのも、受信するのも、大嫌いである。
チマチマチマチマ・・・・・小っこい画面を凝視しながらメールを打ってると侘しくなる。 キーボードだとあっという間に入力できる文章も携帯で入力するとメンドクサイったらありゃしない。 「用件はともかく、返事がほしいならばメールはPCに送れ返事するかしないかは別として」と叫びたい。
携帯で受信したメールを読むのは大嫌いだ。 小っこい画面を凝視しながら小さい字をフムフム・・・・・・と上から下にチマチマと画面をスクロールさせながら読んでいく・・・・・・「あーメンドクサ、イーからもっといっぺんにダーッと表示しろっ!ともかく」と人前もはばからず絶叫しながら携帯を「ドーン!」と窓の外に放り投げてやりたくなる。 だが、もしかすると重要な用件がそこに記されているのかもしれない。 ムカツク半面、携帯電話というものはしみじみと便利なものなのである。
「お、おーっ、へぇ、ふーん」と携帯で受信したメールを読み進む。 送り主は3年ぶりにぐらいに連絡があった人物で、顔を思い浮かべるのも大変なほど付き合いがない。 そんな彼がよこしたメールには、イイ感じのワインバーについての事細やかな情報が記されてあった。
そのワインバーというのは長崎近隣にあり、ワインバーというぐらいだから、ワインにめっぽう強く、しかもバーテンはカワイイ姉ちゃんで、そのカワイイ姉ちゃんがまたワインについて知りすぎていて云々・・・というまさに今すぐその店に飛んでいきたくなるような情報で、スパムメールをばらまいていい気になっている人々も見習うべきであろうという読んでいる人を思わず夢中にさせる充実の内容が記されていたわけである。
長崎から高速使えば2時間だ。 知人もいるし、宿の心配もない。 早速そのワインバーに出向いた。
どこか昭和を感じさせる、ウワサ通りのカワイイ女バーテンは少し「シイナリンゴ」に似ている。 淡々とワインの説明を始める。 「このワインはフニャララで、ウンダラカンタラの、ワインです」と両手で持つワインの簡単な説明をし、バーに座る客のグラスに、そのワインを注いでいく。 要は、ワインを一本あけたら、そのワインを客全員で吟味するというわけだ。 「オイだけ別のワインを飲んじゃるけぇね」という抜け駆けは許されない。 皆で、一本のワインの味を、楽しみ、分析するわけである。
ワイン一杯の値段は定額制であり、上等なワインでも、ヘボいワインでも、一杯は同じ値段である。 と、いうことは、そのワインが旨いかどうかの判断は、それぞれの客に委ねられているわけで、たとえばその昭和美人が注いだワインが安ワインだった場合、バーに座る客は皆、その安ワイン飲んでいるわけで、味のわからない客が、一口飲んでイキがってその安ワインについていっぱしの「うーん、ウマイ、滋味がある。」なんていうなんちゃって評論をしようものならば、周囲の常連客の熱くて冷めた視線を受け続け、退場というという結果に陥ってしまう。 いわば自己責任の世界だ。
オイはこの店の常連でもないし、ワインのことなんてよくわからないので、昭和美人の姉ちゃんが説明するがまま、ワインを楽しんだ。 常連客が言うほど、それぞれのワインの品質に差があるとはおもえない。 どれもうまい。 非常によい店である。 腰をすえてワインを楽しもう。
オイの右となりに座るなべおさみ似の男は、ゼロハリバートンをひざの上で開け広げ、思わず目を疑うほどの携帯電話の山をかき分けつつ、ワインを楽しんでいる。 この男の職業は一体・・・。
店の隅っこで、なにやら中声で怒鳴っている客がいる。 ワインの味について文句を言っているらしいのだが、このテの人物は、世の中に存在する全ての事柄に対してイチャモンをつけるヤツである。即刻退場頂きたいと皆も思っているようだ。
ワインが美味しいし、居心地もよいし、気分がよい。 サントリーサタデーウエイティングバーのように、聞き耳を立てながら、ワインをグビグビ飲る。
左隣に人が座っていることに今気づいた。 小柄な、年のころ70前後の男がワインを飲んでいる。 一瞬視線を向けると、異様なスピードでそれに反応し、ギロリと力強い目でオイの顔を見上げる。 「どうも・・・」と会釈をする。 「う、あぁ・・・・」と男は返事をする。 しばらく沈黙が続いた後、男が話しかけてきた。 「あ、あんた、どっから来たんだい?」
長崎県でありますると答える。
「長崎にはね、3月に行ってきたんですよ。 帝国ホテルに入っている洋菓子屋を贔屓にしていたところ、日ごろの感謝の気持ちをこめて、航空券をプレゼントされたもんだからね。 宿は全日空ホテルでした。」
「しかし長崎ってなかなかいいところだね。 ボクはね、この前デパートで買い物していたら、九州旅行が当たるキャンペーンをしているとかで、抽選会場を案内されたんです。 しかしね、キッパリと断ってやったんです。 旅行ぐらい、自分の金で行きますよ。 金だってカードだって財布に入っている(ここで2つ折の財布を取り出して、広げて中身を見せる一万円札の束がおそらく10万単位で閉じられていて、その束が少なくとも20は入っていた様子)。」
「うわ、すごいですね。 一束ぐらい頂戴できませんか」なんていう冗談が通じない人物のような気がするので、大げさに驚くだけにしておく。
「鯛はね、明石まで食いに行かないと旨くねぇんだよ。 ○○電気の社長とは昔仲がよくて、よくしてもらってたんだよ。 オマエ有名になりたいのか、それとも金が欲しいのか、どっちだ? って聞かれて、オレは金って答えたんだよ。 そしたら当時の金で10億作ってくれたんだよ。 毎日証券会社や銀行からしょっちゅう電話がかかって来るんだよ。 今、醤油屋に五億投資してんだよetc…………」
と、いう風に自慢話というか自伝を沢山聞かされた。 それらの話が真実なのかどうかは知る由もない。 このままだと、あと2時間ぐらいは語られそうな雰囲気だったので、ワインバーから脱出した。
さて。 まだ帰りたくない。 少し小腹もすいたし。 どうしようか。 あ、白レバー。
先日白レバーという鳥の脂肪肝を食べさせてくれる焼鳥屋があるという話を聞いており、ここからそう遠くはないハズなので、タクシーに乗り込み向かう。 おそらくこのあたりだろうというところまで来ているハズなのだが、なかなか見つからない。 情報提供者本人と電話でしゃべりつつ、タクシーの運転手さんに指示をする。 「あ、もう一コ隣の道らしいですスンマセン」
着いた。 ビルの一階にあり、外観だけでいうと、若者相手の店であるような気がし、あまり旨いものを食べさせてくれそうな雰囲気はしない。 しかし白レバーのためだ。 思い切って入店する。 大将らしい男は焼き鳥を焼くのに夢中で、オイが入店したことにも気づいていない様子。 「コンチハー」と声をだすと「あ、オイス、いらっしゃいませーぇ」と力みすぎながら叫ぶ。 カウンターの隅が空いており、そこへ座れと言われる。 若干不安になりながらも腰をおろす。
目の前に空のカップ酒があり、手にとってよく見ると奥播磨であった。 これに使用済みの串を入れていくわけだ。 オイの右隣には、竹村健一似の男が座っており、焼き鳥をほうばる。 アルバイトのニイチャンの頭はピンク色をしている。 さ、状況は把握できた。 早速、白レバーとやらを楽しもうではないか。 メニューを手に取る。 白レバー刺の文字を見つける。 ピンクニイチャンを呼び寄せ、鶏刺盛り合わせと白レバー刺、さらに焼き鳥数本をみつくろってもってきてと注文する。 酒についてはもう少し悩んでみようか。
「白レバー、終わりましたー!」
と、大将がカウンター越しに言う。 「えぇえぇーっつっつ!!」オイは白レバーを食べるためにわざわざ来たのだ。 それなのにそれが無いなんて、こんなムゴい話はない。 「いやー実は○○ちゃんからこの店のことを聞いて、白レバーが美味しいから食べてみてという話だったので楽しみに来てみたんですよ」
「あ、そー、わざわざありがとうね。 ちょっと待ってね(ガザゴソ)白レバー焼きならばあと2本は用意できそうだけどどうする?」
是非お願いします。 刺しは無いが焼きはあった。 よかった。 ○○ちゃんの名前を出してから急に大将との距離が縮まったみたいで、焼きながらイロイロと話しかけてくる。 色々と珍しい日本酒があるようなので、リストの上から順番に飲み進んでやろうと考えて 「すみません、これ、この酒お願いします」と大将に伝える。 指差している酒をチラリと見てから「もっと旨いのあるよ」と嬉しいのか怒っているのかよくわからない表情で言う。 じゃ、そのオススメでお願いします。 出された酒は村裕というもので大変美味しかった。 焼き鳥をワシワシとほうばりながら、オススメの日本酒を次々と飲み干す。 旭若松もうまい。 福島県の女性杜氏が作っている酒というのもよかった。
段々イイ気分になりつつ、次は焼酎をもらい、鳥刺しで飲む。 ささみはモチモチと弾力があり、筋肉の繊維一本一本がハッキリとわかる。 砂肝の刺身は、鮮やかなピンク色をしておりシャキシャキとした食感がステキだ。 これほど美しい鳥の刺身には出会ったことが無い。
時折「ふーっ・・・・ふーっ・・・」という息遣いが聞こえてくる。 これは焼き鳥を一心不乱に焼き続けている大将から発せられるものであり、別に仕事をやりたくなくてため息をつきながら焼き鳥を焼いているとかそういうわけではなくて、焼き台からあがる炎を吹き消しているのである。 焼き台は非常にコンパクトで、よくこんなに小さい焼き台で客の注文をさばけるものだと感心する。 炭と焼き鳥の間にはほとんどスキマが無い。 最早炭の上に焼き鳥を乗せて焼いているといっても過言ではないぐらいだ。 このメチャ近火が、この店の焼き鳥が旨い秘訣なのかもしれないし、ただ単に能率の問題で、早く焼き上げるためだけなのかもしれない。
大将も段々と気持ちよくなってきたらしく、店内についての説明を勝手に始める。 「ウチの皿はね、カッコイイでしょ。 これわざわざウチ用に焼いてもらってんのよ。 このぐい飲みも同じところで焼いてもらってんのよ。 でもね、ぐい飲みは酒が漏るのよね。」
「ウチは割り箸使わないんだよね。 環境にもよくないし。 この箸は一本一本削りだしてもらってんの。 だからさ、箸先がピタリと合うでしょうムハハ、漆が剥げたらまた塗りなおしてもらうわけ」
このように、随所にこだわりが見られるお店なのである。
隣の竹村氏は携帯電話でシャツがどうのこうのという話をかれこれ30分ほど続けており、どうやらオーダーしたシャツの出来がイマイチであるというようなことをしゃべっているらしい。 ちょっと会話をしてみたところ、自分は無職なのだとか、家が4つあるとか、現金しか信用しないとかいうことを熱く語る。 どうやら今日は金持ち(おそらく)と縁があるようである。
そういえば、白レバー焼きどうなったんだろう? 皿に一本も串が残っていないところをみると、知らないうちに食ってしまったのだろう。 おそらくウマカッタんだろうきっと。